慈しみの女神たち <上> [戦争小説]
ど~も。ヴィトゲンシュタインです。
ジョナサン・リテル著の「慈しみの女神たち <上>」を読破しました。
昨年の5月に発売された本書は、神保町の大きな本屋さんでも当時、何冊も積まれていて、
手に取ったことがありますが、ハードカバーの上巻だけでも560ページ、4725円という
ほとんど犯罪的な小説なので、気になりつつも指を咥えるしかありませんでした。
図書館では上下巻が1冊ずつありましたが、予約件数が上昇の一途を辿るにつれ、
4冊へと増量・・。試しに予約してみたら2日後には上下巻が借りられました。
原著は2006年の発刊で、当時38歳の米国人著者による仏語。
アカデミー・フランセーズ文学大賞などを受賞した、ナチスの殺人者の回想という形式の小説です。
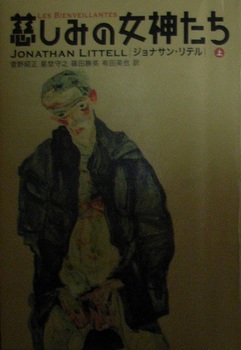
「ユダヤ人に対して、銃5丁は多すぎる」と指示を出す第6軍司令官のフォン・ライヒェナウ元帥。
「かしこまりました。閣下」と敬礼するSS大佐のブローベル・・。
主人公の"わたし"は、彼らに追随するSS中尉のマキシミリアン・アウエ博士ですが、
彼が特に1941年6月の「バルバロッサ作戦」におけるルントシュテットの南方軍集団に属する、
ラッシュ博士のアインザッツグルッペCのゾンダーコマンドのSD部員である・・ということは
事前に紹介されないので、読み進めながら理解していくことになります。
そして銃2丁で確実に射殺するには頭部を狙う必要もあり、
射殺しなければならないウクライナのユダヤ人の数は膨大・・。
このような状況で早々に精神に異常をきたし、一時送還される
ゾンダーコマンド隊長のブローベルSS大佐。

所々で主人公の子供時代や青年時代の回想が出てきますが、
彼が1939年に法学の博士課程を修了し、SD(SS保安部)に入った経緯はこんなところです。
同性愛者である彼がその容疑で検挙されますが、
ゲシュタポの「男色撲滅課」課長マイジンガーが知ったら大変だよ・・と
脅されて、しぶしぶSDに・・。
幕僚部に配属されているアウエは、直接、ユダヤ人を射殺することはありませんが、
隊員はサディズムの反応を見せる者も出る反面、自殺者も2名・・。
武装SSによる死刑囚の公開処刑は銃殺ではなく、見せしめのための絞首刑。。

処刑命令はライヒェナウによるものですが、国防軍兵士はSSの残虐なやり方に苦情をあげる始末。
「卑怯な連中だ。国防軍の糞野郎どもは手を汚したくないんだ・・」
やがて作戦対象はユダヤ人から、住民全員へと拡大。
隊長ブローベルも含め、このSS全国指導者ヒムラーの命令に将校全員が愕然とするのでした。

そして始まった「大作戦」。
警官やウクライナ人の「アスカリ」も動員して、休みなく続く処刑。
疲労困憊して休憩に戻ってきた隊員が缶詰をを開けると、それは「腸詰」。
「こんな食べ物はないだろう!」と怒り狂い、嘔吐する隊員たち・・。
遂にアウエにも交代要員として「止めを刺す」仕事が回ってくるのでした・・。
このユダヤ人を集めて銃殺するシーンはなかなか壮絶なものがありますが、
これは「普通の人びと -ホロコーストと第101警察予備大隊-」とかなり似ていましたので、
参考にしている可能性もありますね。

キエフではベルリンでの知人、ユダヤ人担当の課長となったアイヒマンと再会。
アウエはここで、ユダヤ人問題について全般的な詳しい説明を受けることになります。
さらにミンスクでの爆発物を使ったテスト結果が散々であったことで運ばれてきた
新方式の「ガス・トラック」・・・、
これを思いついたのは保安警察長官でアインザッツグルッペB司令官のネーベです。

あくまで小説ですが、登場実物は第6軍を率いるライヒェナウに
ヒムラー、ハイドリヒ、アイヒマンといった有名人が登場します。
気になって調べてみると、アウエの上官たち、パウル・ブローベルや、
その後任のエルヴィン・ヴァインマンなども実際、アインザッツグルッペCに属する
ゾンダーコマンド4aの司令官なんですね。
ただ、このアインザッツグルッペを構成する「アインザッツコマンド」と「ゾンダーコマンド」の
任務の違いがいまひとつ理解できませんでした。

翌年の夏季攻勢ではSS大尉に昇進し、カフカスに派遣されたアウエ。
そこではA軍集団リスト元帥が解任され、総統自らが後任になったと知らされます。
国防軍将校は「すでに国防軍と陸軍を指揮しておられる総統が、一軍集団の指揮をするとは・・」と、
「そのうちひとつの軍、師団となって、最後には前線で伍長となっているかも・・」
しかしバリバリの国家社会主義者であるアウエは「無礼な言い方だ」と冷たく返答します。
やがて殺されたSD将校の後任として、包囲されたスターリングラードへの移動命令が・・。

すでにヘルマン・ホトの救援「冬の嵐作戦」は頓挫したとの情報を知ったアウエですが、
前線では兵士たちが「マンシュタインは来てくれるんですよね?」
「万全の備えをしておくように・・」と情けない思いで言葉を濁すしかありません。
ソ連のスパイとして捕えられた2人の少年は、まるで救ってもらえるかのように
アウエを見つめますが、何もしてやることは出来ず、銃殺刑に処せられます。
これは映画「スターリングラード」でエド・ハリスに殺された少年を思い出しました。

このままパウルスの第6軍と運命を共にするしかないアウエ。
しかし彼は頭に銃弾を受けたものの、一命を取り留め、最後の飛行機で脱出に成功。
偶然の巡り合わせで後遺症も残らず、見舞いにはヒムラーとカルテンブルンナーの姿も・・。
SS少佐へと昇進し、戦功十字章に加え、戦傷章に冷凍肉勲章、1級鉄十字章も授与されます。

退院後は3ヵ月の休暇でベルリンへ。
当初SDで面倒を見てもらったヴェルナー・ベストや、希望する勤務地であるフランスを仕切る
クノッヘンらと面談しますが、適当なポストは見つかりません。
そんなこんなでフランスに住む母と義父を訊ねることにしたアウエ。
しかし翌朝、惨殺された2人の姿を発見するのでした。

この上下2段組みで訳者さんも4人がかりという膨大な文字数の小説を
一字一句ジックリと読んだか・・というと、そうでもありません。
精神の参った主人公の見る「夢」は、トイレから大便がモリモリと溢れ出したりしますし、
少年時代の同性愛を振り返るシーンでは「陰茎を・・」とか、
いくら文学的であろうが、個人的にホ~モの話には興味なし!ですし、
知りたいとも思いませんから、こういう場面は流し読みしてしまいました。
しかし、いくらなんでも冗長すぎるような気もしますね。
よく小説家のデビュー作は、それまでの10数年間溜め込んできた知識を
気合入れて織り込んでしまうから、長く専門的になりがち・・ということも聞きますが、
本書もそれの典型のようにも感じます。
もちろん、最後まで読むと、意味の無いと思っていた箇所が
重要な複線だったりする可能性もありますので、コレは下巻のお楽しみ・・にしておきます。
ジョナサン・リテル著の「慈しみの女神たち <上>」を読破しました。
昨年の5月に発売された本書は、神保町の大きな本屋さんでも当時、何冊も積まれていて、
手に取ったことがありますが、ハードカバーの上巻だけでも560ページ、4725円という
ほとんど犯罪的な小説なので、気になりつつも指を咥えるしかありませんでした。
図書館では上下巻が1冊ずつありましたが、予約件数が上昇の一途を辿るにつれ、
4冊へと増量・・。試しに予約してみたら2日後には上下巻が借りられました。
原著は2006年の発刊で、当時38歳の米国人著者による仏語。
アカデミー・フランセーズ文学大賞などを受賞した、ナチスの殺人者の回想という形式の小説です。
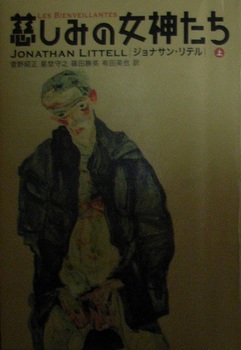
「ユダヤ人に対して、銃5丁は多すぎる」と指示を出す第6軍司令官のフォン・ライヒェナウ元帥。
「かしこまりました。閣下」と敬礼するSS大佐のブローベル・・。
主人公の"わたし"は、彼らに追随するSS中尉のマキシミリアン・アウエ博士ですが、
彼が特に1941年6月の「バルバロッサ作戦」におけるルントシュテットの南方軍集団に属する、
ラッシュ博士のアインザッツグルッペCのゾンダーコマンドのSD部員である・・ということは
事前に紹介されないので、読み進めながら理解していくことになります。
そして銃2丁で確実に射殺するには頭部を狙う必要もあり、
射殺しなければならないウクライナのユダヤ人の数は膨大・・。
このような状況で早々に精神に異常をきたし、一時送還される
ゾンダーコマンド隊長のブローベルSS大佐。

所々で主人公の子供時代や青年時代の回想が出てきますが、
彼が1939年に法学の博士課程を修了し、SD(SS保安部)に入った経緯はこんなところです。
同性愛者である彼がその容疑で検挙されますが、
ゲシュタポの「男色撲滅課」課長マイジンガーが知ったら大変だよ・・と
脅されて、しぶしぶSDに・・。
幕僚部に配属されているアウエは、直接、ユダヤ人を射殺することはありませんが、
隊員はサディズムの反応を見せる者も出る反面、自殺者も2名・・。
武装SSによる死刑囚の公開処刑は銃殺ではなく、見せしめのための絞首刑。。

処刑命令はライヒェナウによるものですが、国防軍兵士はSSの残虐なやり方に苦情をあげる始末。
「卑怯な連中だ。国防軍の糞野郎どもは手を汚したくないんだ・・」
やがて作戦対象はユダヤ人から、住民全員へと拡大。
隊長ブローベルも含め、このSS全国指導者ヒムラーの命令に将校全員が愕然とするのでした。

そして始まった「大作戦」。
警官やウクライナ人の「アスカリ」も動員して、休みなく続く処刑。
疲労困憊して休憩に戻ってきた隊員が缶詰をを開けると、それは「腸詰」。
「こんな食べ物はないだろう!」と怒り狂い、嘔吐する隊員たち・・。
遂にアウエにも交代要員として「止めを刺す」仕事が回ってくるのでした・・。
このユダヤ人を集めて銃殺するシーンはなかなか壮絶なものがありますが、
これは「普通の人びと -ホロコーストと第101警察予備大隊-」とかなり似ていましたので、
参考にしている可能性もありますね。

キエフではベルリンでの知人、ユダヤ人担当の課長となったアイヒマンと再会。
アウエはここで、ユダヤ人問題について全般的な詳しい説明を受けることになります。
さらにミンスクでの爆発物を使ったテスト結果が散々であったことで運ばれてきた
新方式の「ガス・トラック」・・・、
これを思いついたのは保安警察長官でアインザッツグルッペB司令官のネーベです。

あくまで小説ですが、登場実物は第6軍を率いるライヒェナウに
ヒムラー、ハイドリヒ、アイヒマンといった有名人が登場します。
気になって調べてみると、アウエの上官たち、パウル・ブローベルや、
その後任のエルヴィン・ヴァインマンなども実際、アインザッツグルッペCに属する
ゾンダーコマンド4aの司令官なんですね。
ただ、このアインザッツグルッペを構成する「アインザッツコマンド」と「ゾンダーコマンド」の
任務の違いがいまひとつ理解できませんでした。

翌年の夏季攻勢ではSS大尉に昇進し、カフカスに派遣されたアウエ。
そこではA軍集団リスト元帥が解任され、総統自らが後任になったと知らされます。
国防軍将校は「すでに国防軍と陸軍を指揮しておられる総統が、一軍集団の指揮をするとは・・」と、
「そのうちひとつの軍、師団となって、最後には前線で伍長となっているかも・・」
しかしバリバリの国家社会主義者であるアウエは「無礼な言い方だ」と冷たく返答します。
やがて殺されたSD将校の後任として、包囲されたスターリングラードへの移動命令が・・。

すでにヘルマン・ホトの救援「冬の嵐作戦」は頓挫したとの情報を知ったアウエですが、
前線では兵士たちが「マンシュタインは来てくれるんですよね?」
「万全の備えをしておくように・・」と情けない思いで言葉を濁すしかありません。
ソ連のスパイとして捕えられた2人の少年は、まるで救ってもらえるかのように
アウエを見つめますが、何もしてやることは出来ず、銃殺刑に処せられます。
これは映画「スターリングラード」でエド・ハリスに殺された少年を思い出しました。

このままパウルスの第6軍と運命を共にするしかないアウエ。
しかし彼は頭に銃弾を受けたものの、一命を取り留め、最後の飛行機で脱出に成功。
偶然の巡り合わせで後遺症も残らず、見舞いにはヒムラーとカルテンブルンナーの姿も・・。
SS少佐へと昇進し、戦功十字章に加え、戦傷章に冷凍肉勲章、1級鉄十字章も授与されます。
退院後は3ヵ月の休暇でベルリンへ。
当初SDで面倒を見てもらったヴェルナー・ベストや、希望する勤務地であるフランスを仕切る
クノッヘンらと面談しますが、適当なポストは見つかりません。
そんなこんなでフランスに住む母と義父を訊ねることにしたアウエ。
しかし翌朝、惨殺された2人の姿を発見するのでした。

この上下2段組みで訳者さんも4人がかりという膨大な文字数の小説を
一字一句ジックリと読んだか・・というと、そうでもありません。
精神の参った主人公の見る「夢」は、トイレから大便がモリモリと溢れ出したりしますし、
少年時代の同性愛を振り返るシーンでは「陰茎を・・」とか、
いくら文学的であろうが、個人的にホ~モの話には興味なし!ですし、
知りたいとも思いませんから、こういう場面は流し読みしてしまいました。
しかし、いくらなんでも冗長すぎるような気もしますね。
よく小説家のデビュー作は、それまでの10数年間溜め込んできた知識を
気合入れて織り込んでしまうから、長く専門的になりがち・・ということも聞きますが、
本書もそれの典型のようにも感じます。
もちろん、最後まで読むと、意味の無いと思っていた箇所が
重要な複線だったりする可能性もありますので、コレは下巻のお楽しみ・・にしておきます。




おお~、この本は以前からヴィト様が「読みたいな」と仰っていた1冊ですね!
小説に上下巻で9千円と言われましても。。。とはおもいますね。日本の図書館が恋しいです。 タイトルは女神たちなのに、主人公は男なんですね。
レビューをフムフムと読みながら、最後笑ってしまいました。
先日やっと防空壕探検に行けると思い、張り切ってお誘いくれた友人宅に行ったら「森の中だから、入り口がよくわからない!」と言われ、お流れになってしまい、長いこと楽しみにしていた分ガッカリしてしまいました。早めにリベンジしたいです。
by IZM (2012-03-13 17:43)
あららっ?「読みたいな」って言ってましたか・・。最近、記憶が・・。。
まぁ、IZMさんとの関係だから、思いが通じていたとしても、もはや驚きませんが・・。
タイトルについては下巻の最後にチョロっと書いてます。しかし、主人公がホ~モってのは、参りました。なんつったって、「納豆」の次に嫌いなのが「ソレ」ですから、美味しいものを食べている目の前で、納豆かき混ぜられて、気が付いたら鼻で息してなかった・・って感じです。。
だいたい、ホ~モである必要があるのか??って今でもよくわかりません。同性愛者を弾圧したナチスという「皮肉」が込められているのかもしれませんが、この件はあんまり分析する気もないですね。
防空壕探検は残念でしたねぇ。リベンジの記事を楽しみにしています。
by ヴィトゲンシュタイン (2012-03-13 19:55)