ヒトラーの絞首人ハイドリヒ [SS/ゲシュタポ]
ど~も。ヴィトゲンシュタインです。
ロベルト・ゲルヴァルト著の「ヒトラーの絞首人ハイドリヒ」を読破しました。
前回、ホト爺の回顧録を読み終えて、この2年の間にグデーリアンやロンメル、
マンシュタインの本が出版され、次はナニを・・と書きましたが、
独破戦線の休止期間中には第三帝国の軍人だけではなく、
ナチス幹部らに関する本も何冊か出ていました。
例えばローゼンベルクだったり、フライスラーだったり・・。
ですがココは1年半前に出版された、524ページに及ぶハイドリヒ伝を選んでみました。
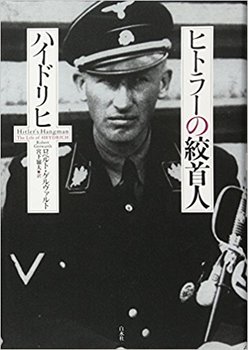
まず巻頭には20枚ほどの写真が・・。
ヒムラー、ゲーリング、カール・ヘルマン・フランクらとの有名な写真から、
パパ・ハイドリヒ、姉マリアとの可愛らしさ溢れる2ショットなどです。

そして第1章は「プラハに死す」。
おっと、主役がいきなり暗殺されてしまうとは。。
この章は20頁に簡潔に書かれており、以前に「暁の七人-ハイドリッヒの暗殺-」や
「HHhH -プラハ、1942年-」など、いろいろ紹介してるので割愛します。
そういえば、『ハイドリヒを撃て 「ナチの野獣」暗殺作戦』、まだ観てないですよねぇ。

第2章は「若きラインハルト」で、父ブルーノの生い立ちから、音楽学校を創設し、
かなりの財力と社会的地位をもった家庭に生まれたラインハルト。
家長として家業を継ぐべく、幼少期からピアノにバイオリンのレッスンを始めます。
しかし1922年、第1次大戦後のインフレ、音楽学校経営の悪化・・という事実の前に
海軍士官の道を歩むことを決意するのでした。。

1930年には美しい19歳の金髪女性リナ・フォン・オステンとの運命的な出会い。
恋の虜となったラインハルトは早速、リナに手紙を書きます。
「ぼくの最愛の最愛のリナ!
ぼくはきみに知ってほしかった。ぼくがきみのことばかり考えてるってことを。
ああ、どんなに深く愛していることか、きみを、きみを!」
書いてる方が恥ずかしいのでコレくらいにしますが、
この当時、リナは確信的なナチ党支持者でバリバリの反ユダヤ主義者、
兄のハンスは3年の党歴を持ち、突撃隊(SA)のメンバーなのでした。

そしてコレまた運命的なベルリンの「女性問題」が発覚します。
本書でも「このベルリンの女性の身元について確実に言えることは、
彼女の父親が海軍上層部に密接なコネクションを持っていたに違いないと
いうことぐらいである」とハッキリしませんね。
ラインハルトの裏切りによって「神経症」になってしまった娘の父親は、
海軍総司令官のレーダーに訴状を提出したことで、軍事名誉法廷で
事情説明を求められたハイドリヒ。
「婚約不履行」は士官の即刻罷免に繋がるほど重大な違法行為ではないものの、
「相手女性が性的関係をリードしたのだ」と主張し、結婚の約束も否認。
自分には何の落ち度もないかのような口ぶりが、3人の海軍軍人の神経を逆なでし、
最終的にはレーダー提督の裁きによって「直ちに罷免」。。

桧山 良昭 著の「ナチス突撃隊」には、
1931年にヨットに乗りたくて入党したSA船舶隊長、ハイドリヒ・・
という記述があってビックリしましたが、本書でもそのような経緯はなく、
とりあえずSSのヒムラーと面談し、無事、舎弟となったハイドリヒ。
ハンブルクのSSで勤務する新人ハイドリヒは、暴れ加減では経験豊富で、
後に盟友となるシュトレッケンバッハに出会い、
共産党などの演説会場への「殴り込み部隊」のリーダーとして急速に悪名を獲得。
ハンブルクの共産党員からは「金髪の野獣」と呼ばれるように・・。
確かにこの章タイトルは「ハイドリヒ誕生」でした。。

ヒムラーが「美しいカップル」と呼んだ、新婚のハイドリヒ夫妻は
ミュンヘン郊外に小さな家を借ります。
そんな新生活も若奥さんのリナにとっては新しい環境の中で孤独の日々。
旦那は新設の「SD」の職務に忙殺されて、家にいる時間はごくわずか。
オマケに旦那の上司ヒムラーの奥さん、マルガレーテとちょいちょい顔を合わせるも
「陳腐な、ユーモアのない女性」と評して、好きになれず・・。

1934年春までにドイツの州のほとんどの政治警察組織を管理下に置いた
ヒムラー&ハイドリヒのコンビですが、最も重要なプロイセン州のゲシュタポも
仕切っているゲーリングをだまくらかしてなんとか掌握。
ハイドリヒはバイエルンの政治警察からハインリヒ・ミュラー、ヨーゼフ・マイジンガー
といった信頼する部下を呼び寄せます。
こうしてレームとSAの粛清、「長いナイフの夜」へ。
勝利と成功を証明したSSがより強力になることをよく思わない勢力も存在します。
内相のフリックはドイツ警察に対する自分の権威がヒムラーとハイドリヒによって
切り崩されていることに苛立ち、レーム事件で数名の将軍が殺害された軍部も同様。
他方、陸軍保守派をイデオロギー的に信用し難いと考えるヒムラー&ハイドリヒ。
もちろん軍の情報部門アプヴェーアのカナリスとの駆け引きも始まってきます。

また奥さんリナの戦いは1937年になっても続いています。
それは頻繁にハイドリヒ家を訪れるヒムラー夫妻。
マルガレーテはSS全国指導者の妻としての風を吹かせてリナに説教し、
「リナと離婚するようハイドリヒに言ってほしい」と旦那に迫るほど。。ひぃぃ、コワイ!

オーストリア併合では、ウィーンに一番乗りした人々の中にヒムラー&ハイドリヒがおり、
一斉逮捕の第一波の指揮と、オーストリア警察の「浄化」に取り組む様子が詳しく。
このあたりは今まで読んだ記憶がなく、興味深かったですね。
続くズデーテンラント問題では、両国政府が全面動員を開始するなか、
ハイドリヒは「アインザッツグルッペン」2個の結成を承認。
次のポーランド戦では、ドイツ軍の侵攻3時間前に書かれたリナ宛ての遺言書が
1ページに渡って掲載されており、コレはかなり印象に残ります。
3回読み直しちゃいました。

第6章「大量殺戮の実験」は、ポーランド戦での「アインザッツグルッペン」の様子が。
ハイドリヒが視察した部隊はシュトレッケンバッハとウード・フォン・ヴォイルシュ。
抵抗分子には最大限の過酷な手段によって対処すべきだと繰り返し、
ユダヤ人については徹底的に弾圧し、独ソ境界線を越えて東方への逃亡を仕向けるよう
命令するハイドリヒと、そんな任務にうってつけの男であるヴォイルシュ。
数日間で500人のユダヤ人の命を奪い、シナゴークで焼殺、農村部で銃殺と努力を倍加。

西プロイセンではヒムラーの個人副官ルドルフ・フォン・アルフェンスレーベン指揮のもと
4000人以上のポーランド人を殺害して、特別の悪名を獲得するのでした。

翌年の「西部戦線」はハイドリヒにとっては敗北の日々。
なぜならポーランド戦でアインザッツグルッペンが過度の暴力を振るったことで
陸軍がSSの参加を拒否。まぁ、武装SSとは別の・・という意味でしょうね。
そんなわけでノルウェー戦線で一時的にドイツ空軍に参加する許可をヒムラーに求めます。
1935年からスポーツパイロットとしての訓練を受けており、ポーランド上空で
射撃手として空戦デビューを果たしていたハイドリヒ。
表向きはどこかの部隊の空軍大尉ということで、4週間、「戦闘機中隊77」に所属して
退却するノルウェー軍を空から襲撃し、同僚士官と酒を酌み交わし、トランプに興じたり。

「自分は元気です」とヒムラーに報告すると、
「終始、君のことを考えている。元気でいて欲しい。
もう一度、君の健勝と無事を祈る!
できることなら毎日便りをしてもらいたい」
と、直ちに返信を送るヒムラー。変な想像はイケませんぜ。。

さらに「バトル・オブ・ブリテン」の航空作戦にもハイドリヒは参加するつもりであり、
英国を征服した際には、アインザッツグルッペンの責任者にはジックスを任命。
ゲシュタポ用のハンドブックを作成しているのはシェレンベルクです。
「GB特別捜査リスト」として挙げているのはチャーチルやイーデンといった政治家の他に
H・G・ウェルズの名前まで・・。
もはや「SS-GB」の世界の一歩手前といった感じですね。
翌1941年は再び、ハイドリヒと彼の「アインザッツグルッペン」の出番がやって来ます。
陸軍補給局長エドゥアルド・ヴァーグナーと交渉し、SSと国防軍の協力で合意します。

ネーベ、ラッシュ、オーレンドルフが率いる各部隊に、
シュターレッカーのA部隊の17人の指導的将校のうち11人は法律家であり、
9人は博士号取得者で、古参党員も多く、ハイドリヒのSDで昇進してきた
40歳未満の高学歴者が中心。彼らは無慈悲さと実践主義を体現したのです。
6月11日、ヒムラーはヴェーヴェルスブルク城にSSの大物たちを招集します。
ハイドリヒにダリューゲ、ヴォルフ、そして占領下ソ連領を管理するために任命された
SS・警察高級指導者のプリュッツマン、バッハ=ツェレウスキ、イェッケルン。
席上、「東ヨーロッパ住民が3000万人は死ぬだろう」と述べるヒムラー。
いや~、スゴイ面子の会議だ。「ヴァンゼー会議」より興味があります。

バルバロッサが始まり、前線後方でパルチザン活動が勢いを増し始めると
国防軍も虐殺行為に対して寛容になったばかりか、自身も喜んで参加するように。
ハイドリヒがアインザッツグルッペンの視察に訪れれば、上司にイイトコ見せようと
いつもより多く殺してしまうのも理解できます。。
そんなころ、ハイドリヒに衝撃的な決定が・・。
対ソ連終結のあかつきには、占領地域は「東部占領地域大臣」ローゼンベルクの
全面的統括下の文民機関によって統治されるというヒトラーの決定です。
SSは新占領地域の治安維持業務に限定されたことで、ハイドリヒはさしずめ
ローゼンベルクとSSの連絡将校というショボイ立場に。。

ローゼンベルクの新占領地域はいくつかの管区に分けられ、各々に特別委員が任命。
その特別委員を絶対的ライバルと見るハイドリヒ・・。
オストラント帝国管区のヒンリヒ・ローゼ、
ウクライナ帝国管区は肥満漢エーリヒ・コッホ、
白ルテニアの行政委員となったヴィルヘルム・クーベは虚栄心が強く腐敗した男で、
1935年にハイドリヒが彼の身辺を捜査した結果、横領で有罪となり、
一時、党の全役職を剥奪されたことでハイドリヒに恨みを抱いている男。
ただナチ党歴が古いというだけで東方での重要な地位に任命されている連中に、
ハイドリヒは嫌悪感を覚えるのでした。

今度はヒムラーに内緒で、Bf109に乗り込んだハイドリヒ。
この機はウーデットから、夜間の空襲中にベルリンを通行する特別の警察許可を
与えるのと引き換えに借りていたようですが、辿り着いた部隊はまたも「戦闘機中隊77」。
コレは翻訳の問題か、おそらく第77戦闘航空団(JG77)だと思います。

そしてハイドリヒは対空砲火により被弾し、ロシア軍前線付近に不時着。
数時間後、斥候兵が不時着したパイロットを救出の報告が入ります。
しかしそのパイロットは外傷はないものの、脳に損傷を受けている可能性が・・。
自分のことを「RSHA長官」だと言い続けている。。
この直前に英国へ飛んで行き、「自分はナチ党副総裁だ」と言った人を思い出しますねぇ。

アルコール依存や精神障害の例が見られるとの報告を頻繁に受け、
銃殺というアインザッツグルッペンの処刑方法に疑念が出始めると、
いよいよアイヒマンだのガス・トラックだのガス室だのという「ホロコースト」が。
「狂信的で陰険なオーストリア人」と紹介されるのはグロボクニクです。
このように、後世にも名を残す極悪非道のアインザッツグルッペンを指揮し、
ユダヤ人問題の最終的解決を目指す「ヴァンゼー会議」も紹介されたあと、
337頁から第8章「保護領の支配者」が始まります。

ちなみに本書はこれまで語られてきたハイドリヒのイメージ、
すなわちシェレンベルクが「凄まじく野心的」、カール・ヴォルフが「悪魔的」と評した
金髪の野獣ハイドリヒのイメージを踏襲するような伝記ではなく、
あくまで現存する公的な資料、残された手紙、理性的な証言を元に書き起こされており
逆に言えば「ハイドリヒってどんだけ悪い奴やねん・・」という極悪人エピソードの連発に
思わず苦笑いしながら楽しむ本ではありません。
裏の取れないハイドリヒ極悪人伝説は極力排除し、あるいは有名な逸話を紹介した場合でも
「証明されていない」と、あくまで「噂」の域を出ないことを明確にします。
まだバルバロッサとアインザッツグルッペンが進撃中の1941年9月、RSHA長官としての
職はそのままに、ベーメン・メーレン保護領副総督に任命されたハイドリヒ。
総督ノイラートの緩い保護政策を回復させるだけでなく、ベルリン、ウィーンと並び、
プラハが「ユダヤ人ゼロ」とされるべき主要都市の一つとしてヒトラーが選んだことによる
人選であり、それを急速に実行するのにうってつけだったのがハイドリヒ・・というのが
著者の見解です。ふ~ん。なるほどねぇ。。

この対ソ戦の勝利を目前としてベルリンから離れざるを得ないハイドリヒですが、
SS大将及び警察大将に昇進し、口うるさい占領地行政官やガウライターらとの軋轢もなく、
思いっきり自身のSS政策を実行でき、なにより、保護領総督の地位は「総統直属」であり、
ヒトラーとの直接の接触の道を開いたということになるわけです。
そして保護領内の4つの大管区、ズデーテンラント、オーバードナウ、ニーダードナウ、
バイエリッシュ・オストマルクの外見に加え、知的能力も劣ったガウライターらに
攻撃を開始し、最も頑強な抵抗者ニーダードナウのフーゴ・ユリを名指しして、
自分の計画を混乱させる元凶だと痛罵。
非協力的なナチ党官吏たちも容赦なく解任するのでした。

抵抗運動の抑え込み以外にも重要な仕事、それは「保護領のゲルマン化」です。
チェコ人は基本的にスラヴ民族とされているわけですが、SS人種専門家の意見では
チェコ住民の相当数は本来ドイツ系であり、ほぼ50%は貴重なゲルマンの血を
保持しているというもの。
本土からの入植によってドイツの血を再獲得し、増大させることが必要なのです。
例えばドイツ人と結婚したチェコ人女性から生まれてきた子供はドイツ人といった具合。
しかし事柄を複雑にしたのはスラヴ人とは何か、ドイツ人とは何かについて、
なんら明確な定義が無いという事実にハイドリヒも悪戦苦闘。。

1942年3月にはハイドリヒの親密な仲間でありアインザッツグルッペンの指揮官であった
シュターレッカーがパルチザンに殺害されるなど、占領下各地で抵抗運動が激化。
5月、軍政の敷かれたパリでもSSが権力拡大を目指し、ハイドリヒのかつての個人副官
オーベルクを責任者に据えると自身もパリへ飛び、ホテル・リッツで就任式を主宰します。
こうして運命の5月27日の朝をプラハで迎えることになるのでした。

最後の第9章は「破壊の遺産」
ハイドリヒの国葬の様子が詳細に、そして報復となる「リディツェ村の惨劇」と続き、
デスマスクをあしらった「ハイドリヒ記念切手」が発売。
翌年には米国で「死刑執行人もまた死す」が上映。
また、亭主を失ったリナの生活とその戦後。
今回は初めて本書で知った、または興味深いエピソードを中心に紹介しました。
本書でも途中、触れられていたと思いますが、とにかく警官の経験もなく、
警察の仕事は知らない、あるいは一つの国を統治するなどという行政の経験もない
ハイドリヒが次から次へとそれらをこなしていくというのは、単に能力だけではなく、
膨大な仕事量であり、どれだけのエネルギーが必要だったかは、
社会で仕事をした人なら容易に想像がつくでしょう。
しかも「ヒムラーとヒトラー 氷のユートピア」という本がありましたが、
彼らの夢想を実現する、現実化するのがリアリストであるハイドリヒであり、
その部下をコントロールする手腕と、敵対する官庁への根回しや調整能力といったものも
抜群だったのではないか・・と想像できます。

ヒムラーのように1900年生まれとか、ハイドリヒのような1904年生まれというのは
ちょっと兄貴の世代、5歳年上、場合によっては1歳年上の人が第1次大戦に従軍しており、
男として、その軍人としての経験を味わうことなく育ったという劣等感がある気がします。
軍の前線に追随し、命の危険もあるアインザッツグルッペンに若いエリートを派遣したり、
今次大戦が続いているうちに、戦闘機パイロットとして活躍しておきたいという願望など
単にSSという組織で出世することだけが目標ではない、
自身の理想とする男としての渇望がハイドリヒを一心不乱に向かわせたのではないか?
そんな風にも感じました。

例えばプラハで護衛も付けずにオープンカーに乗っていたのも、
「私がドイツ国民に襲われるわけがない」と公言し、オープンカーに乗っていた
1930年代のヒトラーを彷彿とさせますし、襲撃された際も、
全速力で逃げればよいものを、わざわざ停車させて拳銃を抜き、自ら暗殺者を
倒そうとする行動は、ここまで成り上がって来た彼の生き様そのものにも思えます。
良くも悪くも、丸々1週間ほどハイドリヒと向き合う生活を送り、
精神的にもグッタリと疲れた1週間となりました。
ロベルト・ゲルヴァルト著の「ヒトラーの絞首人ハイドリヒ」を読破しました。
前回、ホト爺の回顧録を読み終えて、この2年の間にグデーリアンやロンメル、
マンシュタインの本が出版され、次はナニを・・と書きましたが、
独破戦線の休止期間中には第三帝国の軍人だけではなく、
ナチス幹部らに関する本も何冊か出ていました。
例えばローゼンベルクだったり、フライスラーだったり・・。
ですがココは1年半前に出版された、524ページに及ぶハイドリヒ伝を選んでみました。
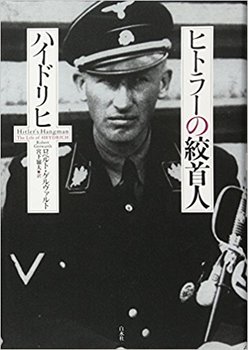
まず巻頭には20枚ほどの写真が・・。
ヒムラー、ゲーリング、カール・ヘルマン・フランクらとの有名な写真から、
パパ・ハイドリヒ、姉マリアとの可愛らしさ溢れる2ショットなどです。

そして第1章は「プラハに死す」。
おっと、主役がいきなり暗殺されてしまうとは。。
この章は20頁に簡潔に書かれており、以前に「暁の七人-ハイドリッヒの暗殺-」や
「HHhH -プラハ、1942年-」など、いろいろ紹介してるので割愛します。
そういえば、『ハイドリヒを撃て 「ナチの野獣」暗殺作戦』、まだ観てないですよねぇ。

第2章は「若きラインハルト」で、父ブルーノの生い立ちから、音楽学校を創設し、
かなりの財力と社会的地位をもった家庭に生まれたラインハルト。
家長として家業を継ぐべく、幼少期からピアノにバイオリンのレッスンを始めます。
しかし1922年、第1次大戦後のインフレ、音楽学校経営の悪化・・という事実の前に
海軍士官の道を歩むことを決意するのでした。。

1930年には美しい19歳の金髪女性リナ・フォン・オステンとの運命的な出会い。
恋の虜となったラインハルトは早速、リナに手紙を書きます。
「ぼくの最愛の最愛のリナ!
ぼくはきみに知ってほしかった。ぼくがきみのことばかり考えてるってことを。
ああ、どんなに深く愛していることか、きみを、きみを!」
書いてる方が恥ずかしいのでコレくらいにしますが、
この当時、リナは確信的なナチ党支持者でバリバリの反ユダヤ主義者、
兄のハンスは3年の党歴を持ち、突撃隊(SA)のメンバーなのでした。

そしてコレまた運命的なベルリンの「女性問題」が発覚します。
本書でも「このベルリンの女性の身元について確実に言えることは、
彼女の父親が海軍上層部に密接なコネクションを持っていたに違いないと
いうことぐらいである」とハッキリしませんね。
ラインハルトの裏切りによって「神経症」になってしまった娘の父親は、
海軍総司令官のレーダーに訴状を提出したことで、軍事名誉法廷で
事情説明を求められたハイドリヒ。
「婚約不履行」は士官の即刻罷免に繋がるほど重大な違法行為ではないものの、
「相手女性が性的関係をリードしたのだ」と主張し、結婚の約束も否認。
自分には何の落ち度もないかのような口ぶりが、3人の海軍軍人の神経を逆なでし、
最終的にはレーダー提督の裁きによって「直ちに罷免」。。

桧山 良昭 著の「ナチス突撃隊」には、
1931年にヨットに乗りたくて入党したSA船舶隊長、ハイドリヒ・・
という記述があってビックリしましたが、本書でもそのような経緯はなく、
とりあえずSSのヒムラーと面談し、無事、舎弟となったハイドリヒ。
ハンブルクのSSで勤務する新人ハイドリヒは、暴れ加減では経験豊富で、
後に盟友となるシュトレッケンバッハに出会い、
共産党などの演説会場への「殴り込み部隊」のリーダーとして急速に悪名を獲得。
ハンブルクの共産党員からは「金髪の野獣」と呼ばれるように・・。
確かにこの章タイトルは「ハイドリヒ誕生」でした。。

ヒムラーが「美しいカップル」と呼んだ、新婚のハイドリヒ夫妻は
ミュンヘン郊外に小さな家を借ります。
そんな新生活も若奥さんのリナにとっては新しい環境の中で孤独の日々。
旦那は新設の「SD」の職務に忙殺されて、家にいる時間はごくわずか。
オマケに旦那の上司ヒムラーの奥さん、マルガレーテとちょいちょい顔を合わせるも
「陳腐な、ユーモアのない女性」と評して、好きになれず・・。

1934年春までにドイツの州のほとんどの政治警察組織を管理下に置いた
ヒムラー&ハイドリヒのコンビですが、最も重要なプロイセン州のゲシュタポも
仕切っているゲーリングをだまくらかしてなんとか掌握。
ハイドリヒはバイエルンの政治警察からハインリヒ・ミュラー、ヨーゼフ・マイジンガー
といった信頼する部下を呼び寄せます。
こうしてレームとSAの粛清、「長いナイフの夜」へ。
勝利と成功を証明したSSがより強力になることをよく思わない勢力も存在します。
内相のフリックはドイツ警察に対する自分の権威がヒムラーとハイドリヒによって
切り崩されていることに苛立ち、レーム事件で数名の将軍が殺害された軍部も同様。
他方、陸軍保守派をイデオロギー的に信用し難いと考えるヒムラー&ハイドリヒ。
もちろん軍の情報部門アプヴェーアのカナリスとの駆け引きも始まってきます。

また奥さんリナの戦いは1937年になっても続いています。
それは頻繁にハイドリヒ家を訪れるヒムラー夫妻。
マルガレーテはSS全国指導者の妻としての風を吹かせてリナに説教し、
「リナと離婚するようハイドリヒに言ってほしい」と旦那に迫るほど。。ひぃぃ、コワイ!

オーストリア併合では、ウィーンに一番乗りした人々の中にヒムラー&ハイドリヒがおり、
一斉逮捕の第一波の指揮と、オーストリア警察の「浄化」に取り組む様子が詳しく。
このあたりは今まで読んだ記憶がなく、興味深かったですね。
続くズデーテンラント問題では、両国政府が全面動員を開始するなか、
ハイドリヒは「アインザッツグルッペン」2個の結成を承認。
次のポーランド戦では、ドイツ軍の侵攻3時間前に書かれたリナ宛ての遺言書が
1ページに渡って掲載されており、コレはかなり印象に残ります。
3回読み直しちゃいました。

第6章「大量殺戮の実験」は、ポーランド戦での「アインザッツグルッペン」の様子が。
ハイドリヒが視察した部隊はシュトレッケンバッハとウード・フォン・ヴォイルシュ。
抵抗分子には最大限の過酷な手段によって対処すべきだと繰り返し、
ユダヤ人については徹底的に弾圧し、独ソ境界線を越えて東方への逃亡を仕向けるよう
命令するハイドリヒと、そんな任務にうってつけの男であるヴォイルシュ。
数日間で500人のユダヤ人の命を奪い、シナゴークで焼殺、農村部で銃殺と努力を倍加。

西プロイセンではヒムラーの個人副官ルドルフ・フォン・アルフェンスレーベン指揮のもと
4000人以上のポーランド人を殺害して、特別の悪名を獲得するのでした。

翌年の「西部戦線」はハイドリヒにとっては敗北の日々。
なぜならポーランド戦でアインザッツグルッペンが過度の暴力を振るったことで
陸軍がSSの参加を拒否。まぁ、武装SSとは別の・・という意味でしょうね。
そんなわけでノルウェー戦線で一時的にドイツ空軍に参加する許可をヒムラーに求めます。
1935年からスポーツパイロットとしての訓練を受けており、ポーランド上空で
射撃手として空戦デビューを果たしていたハイドリヒ。
表向きはどこかの部隊の空軍大尉ということで、4週間、「戦闘機中隊77」に所属して
退却するノルウェー軍を空から襲撃し、同僚士官と酒を酌み交わし、トランプに興じたり。
「自分は元気です」とヒムラーに報告すると、
「終始、君のことを考えている。元気でいて欲しい。
もう一度、君の健勝と無事を祈る!
できることなら毎日便りをしてもらいたい」
と、直ちに返信を送るヒムラー。変な想像はイケませんぜ。。

さらに「バトル・オブ・ブリテン」の航空作戦にもハイドリヒは参加するつもりであり、
英国を征服した際には、アインザッツグルッペンの責任者にはジックスを任命。
ゲシュタポ用のハンドブックを作成しているのはシェレンベルクです。
「GB特別捜査リスト」として挙げているのはチャーチルやイーデンといった政治家の他に
H・G・ウェルズの名前まで・・。
もはや「SS-GB」の世界の一歩手前といった感じですね。
翌1941年は再び、ハイドリヒと彼の「アインザッツグルッペン」の出番がやって来ます。
陸軍補給局長エドゥアルド・ヴァーグナーと交渉し、SSと国防軍の協力で合意します。

ネーベ、ラッシュ、オーレンドルフが率いる各部隊に、
シュターレッカーのA部隊の17人の指導的将校のうち11人は法律家であり、
9人は博士号取得者で、古参党員も多く、ハイドリヒのSDで昇進してきた
40歳未満の高学歴者が中心。彼らは無慈悲さと実践主義を体現したのです。
6月11日、ヒムラーはヴェーヴェルスブルク城にSSの大物たちを招集します。
ハイドリヒにダリューゲ、ヴォルフ、そして占領下ソ連領を管理するために任命された
SS・警察高級指導者のプリュッツマン、バッハ=ツェレウスキ、イェッケルン。
席上、「東ヨーロッパ住民が3000万人は死ぬだろう」と述べるヒムラー。
いや~、スゴイ面子の会議だ。「ヴァンゼー会議」より興味があります。

バルバロッサが始まり、前線後方でパルチザン活動が勢いを増し始めると
国防軍も虐殺行為に対して寛容になったばかりか、自身も喜んで参加するように。
ハイドリヒがアインザッツグルッペンの視察に訪れれば、上司にイイトコ見せようと
いつもより多く殺してしまうのも理解できます。。
そんなころ、ハイドリヒに衝撃的な決定が・・。
対ソ連終結のあかつきには、占領地域は「東部占領地域大臣」ローゼンベルクの
全面的統括下の文民機関によって統治されるというヒトラーの決定です。
SSは新占領地域の治安維持業務に限定されたことで、ハイドリヒはさしずめ
ローゼンベルクとSSの連絡将校というショボイ立場に。。

ローゼンベルクの新占領地域はいくつかの管区に分けられ、各々に特別委員が任命。
その特別委員を絶対的ライバルと見るハイドリヒ・・。
オストラント帝国管区のヒンリヒ・ローゼ、
ウクライナ帝国管区は肥満漢エーリヒ・コッホ、
白ルテニアの行政委員となったヴィルヘルム・クーベは虚栄心が強く腐敗した男で、
1935年にハイドリヒが彼の身辺を捜査した結果、横領で有罪となり、
一時、党の全役職を剥奪されたことでハイドリヒに恨みを抱いている男。
ただナチ党歴が古いというだけで東方での重要な地位に任命されている連中に、
ハイドリヒは嫌悪感を覚えるのでした。

今度はヒムラーに内緒で、Bf109に乗り込んだハイドリヒ。
この機はウーデットから、夜間の空襲中にベルリンを通行する特別の警察許可を
与えるのと引き換えに借りていたようですが、辿り着いた部隊はまたも「戦闘機中隊77」。
コレは翻訳の問題か、おそらく第77戦闘航空団(JG77)だと思います。

そしてハイドリヒは対空砲火により被弾し、ロシア軍前線付近に不時着。
数時間後、斥候兵が不時着したパイロットを救出の報告が入ります。
しかしそのパイロットは外傷はないものの、脳に損傷を受けている可能性が・・。
自分のことを「RSHA長官」だと言い続けている。。
この直前に英国へ飛んで行き、「自分はナチ党副総裁だ」と言った人を思い出しますねぇ。

アルコール依存や精神障害の例が見られるとの報告を頻繁に受け、
銃殺というアインザッツグルッペンの処刑方法に疑念が出始めると、
いよいよアイヒマンだのガス・トラックだのガス室だのという「ホロコースト」が。
「狂信的で陰険なオーストリア人」と紹介されるのはグロボクニクです。
このように、後世にも名を残す極悪非道のアインザッツグルッペンを指揮し、
ユダヤ人問題の最終的解決を目指す「ヴァンゼー会議」も紹介されたあと、
337頁から第8章「保護領の支配者」が始まります。

ちなみに本書はこれまで語られてきたハイドリヒのイメージ、
すなわちシェレンベルクが「凄まじく野心的」、カール・ヴォルフが「悪魔的」と評した
金髪の野獣ハイドリヒのイメージを踏襲するような伝記ではなく、
あくまで現存する公的な資料、残された手紙、理性的な証言を元に書き起こされており
逆に言えば「ハイドリヒってどんだけ悪い奴やねん・・」という極悪人エピソードの連発に
思わず苦笑いしながら楽しむ本ではありません。
裏の取れないハイドリヒ極悪人伝説は極力排除し、あるいは有名な逸話を紹介した場合でも
「証明されていない」と、あくまで「噂」の域を出ないことを明確にします。
まだバルバロッサとアインザッツグルッペンが進撃中の1941年9月、RSHA長官としての
職はそのままに、ベーメン・メーレン保護領副総督に任命されたハイドリヒ。
総督ノイラートの緩い保護政策を回復させるだけでなく、ベルリン、ウィーンと並び、
プラハが「ユダヤ人ゼロ」とされるべき主要都市の一つとしてヒトラーが選んだことによる
人選であり、それを急速に実行するのにうってつけだったのがハイドリヒ・・というのが
著者の見解です。ふ~ん。なるほどねぇ。。

この対ソ戦の勝利を目前としてベルリンから離れざるを得ないハイドリヒですが、
SS大将及び警察大将に昇進し、口うるさい占領地行政官やガウライターらとの軋轢もなく、
思いっきり自身のSS政策を実行でき、なにより、保護領総督の地位は「総統直属」であり、
ヒトラーとの直接の接触の道を開いたということになるわけです。
そして保護領内の4つの大管区、ズデーテンラント、オーバードナウ、ニーダードナウ、
バイエリッシュ・オストマルクの外見に加え、知的能力も劣ったガウライターらに
攻撃を開始し、最も頑強な抵抗者ニーダードナウのフーゴ・ユリを名指しして、
自分の計画を混乱させる元凶だと痛罵。
非協力的なナチ党官吏たちも容赦なく解任するのでした。

抵抗運動の抑え込み以外にも重要な仕事、それは「保護領のゲルマン化」です。
チェコ人は基本的にスラヴ民族とされているわけですが、SS人種専門家の意見では
チェコ住民の相当数は本来ドイツ系であり、ほぼ50%は貴重なゲルマンの血を
保持しているというもの。
本土からの入植によってドイツの血を再獲得し、増大させることが必要なのです。
例えばドイツ人と結婚したチェコ人女性から生まれてきた子供はドイツ人といった具合。
しかし事柄を複雑にしたのはスラヴ人とは何か、ドイツ人とは何かについて、
なんら明確な定義が無いという事実にハイドリヒも悪戦苦闘。。

1942年3月にはハイドリヒの親密な仲間でありアインザッツグルッペンの指揮官であった
シュターレッカーがパルチザンに殺害されるなど、占領下各地で抵抗運動が激化。
5月、軍政の敷かれたパリでもSSが権力拡大を目指し、ハイドリヒのかつての個人副官
オーベルクを責任者に据えると自身もパリへ飛び、ホテル・リッツで就任式を主宰します。
こうして運命の5月27日の朝をプラハで迎えることになるのでした。

最後の第9章は「破壊の遺産」
ハイドリヒの国葬の様子が詳細に、そして報復となる「リディツェ村の惨劇」と続き、
デスマスクをあしらった「ハイドリヒ記念切手」が発売。
翌年には米国で「死刑執行人もまた死す」が上映。
また、亭主を失ったリナの生活とその戦後。
今回は初めて本書で知った、または興味深いエピソードを中心に紹介しました。
本書でも途中、触れられていたと思いますが、とにかく警官の経験もなく、
警察の仕事は知らない、あるいは一つの国を統治するなどという行政の経験もない
ハイドリヒが次から次へとそれらをこなしていくというのは、単に能力だけではなく、
膨大な仕事量であり、どれだけのエネルギーが必要だったかは、
社会で仕事をした人なら容易に想像がつくでしょう。
しかも「ヒムラーとヒトラー 氷のユートピア」という本がありましたが、
彼らの夢想を実現する、現実化するのがリアリストであるハイドリヒであり、
その部下をコントロールする手腕と、敵対する官庁への根回しや調整能力といったものも
抜群だったのではないか・・と想像できます。

ヒムラーのように1900年生まれとか、ハイドリヒのような1904年生まれというのは
ちょっと兄貴の世代、5歳年上、場合によっては1歳年上の人が第1次大戦に従軍しており、
男として、その軍人としての経験を味わうことなく育ったという劣等感がある気がします。
軍の前線に追随し、命の危険もあるアインザッツグルッペンに若いエリートを派遣したり、
今次大戦が続いているうちに、戦闘機パイロットとして活躍しておきたいという願望など
単にSSという組織で出世することだけが目標ではない、
自身の理想とする男としての渇望がハイドリヒを一心不乱に向かわせたのではないか?
そんな風にも感じました。

例えばプラハで護衛も付けずにオープンカーに乗っていたのも、
「私がドイツ国民に襲われるわけがない」と公言し、オープンカーに乗っていた
1930年代のヒトラーを彷彿とさせますし、襲撃された際も、
全速力で逃げればよいものを、わざわざ停車させて拳銃を抜き、自ら暗殺者を
倒そうとする行動は、ここまで成り上がって来た彼の生き様そのものにも思えます。
良くも悪くも、丸々1週間ほどハイドリヒと向き合う生活を送り、
精神的にもグッタリと疲れた1週間となりました。
タグ:イェッケルン 長いナイフの夜 レーム リディツェ村 ベーメン・メーレン保護領 RSHA アンシュルス ゲシュタポ カナリス ダリューゲ ハインリッヒ・ミュラー オーベルク sd ズデーテンラント ノイラート エーリッヒ・コッホ シュターレッカー ネーベ シェレンベルク バルバロッサ作戦 ホロコースト グロボクニク カール・ヘルマン・フランク アイヒマン オーレンドルフ ローゼンベルク フリック プリュッツマン マイジンガー ゲーリング シュトレッケンバッハ アインザッツグルッペン ヒムラー レーダー元帥 ハイドリヒ リナ・ハイドリヒ バッハ=ツェレウスキ 死刑執行人もまた死す ヴァンゼー会議 アルフレート・ジックス ヴェーヴェルスブルク カール・ヴォルフ




トップを盲信して、その指示を実行していくのって、体力と頭は使うけど、充実感はあるし、褒めてもらえるし、ある意味、楽な生き方なんですよね。
ハイドリヒの人間性に触れる本をちゃんと読んだことがないんですが、彼もそれなりに自分の仕事を批判的に見つめ直したりすることはあったんでしょうか?この本はその辺も書いてるのかな?
by ヘビースモーカー (2018-05-25 14:28)
がむしゃらに働いて、38歳没ですからねぇ。。
振り返るヒマがあったか?
あったとしても、そんな弱みを見せたり残したりしたか?
ボクはそーは思いません。
ただし、本書にも書いてあったと思いますけど、嫁さんには自分の職務を「第三帝国のゴミ捨て場のトップ」と言っていたとか。
「ゴミ捨て場」をどう解釈するかですが、まぁ、汚れ仕事でイイでしょう。総統のためにどんな汚い、あくどい、クソッタレな仕事でも引き受けると。この本を読むと、その気概があったと感じますね。
by ヴィトゲンシュタイン (2018-05-25 18:58)