赤軍記者グロースマン -独ソ戦取材ノート1941‐45- [ロシア]
ど~も。ヴィトゲンシュタインです。
アントニー・ビーヴァー著の「赤軍記者グロースマン」を読破しました。
過去に「スターリングラード」や「ベルリン陥落 1945」、そして「ベルリン終戦日記」と紹介している
自分の好きな英国の著者、アントニー・ビーヴァーの上下巻の大作、
「ノルマンディー上陸作戦1944」が夏に発売され、「お~、コレ読みたいなぁ・・」と思ったものの、
そういえばグロースマン読んでなかった・・ということに気づきました。
2007年発刊の本書は、ウクライナ生まれのユダヤ人作家グロースマンが、
独ソ戦勃発とともに従軍記者として最前線で見聞きし、それをメモしたノートを中心に、
彼が緒戦の「キエフ大包囲」から「スターリングラード」を経て、ベルリンに至るまでを
著者ビーヴァーの戦局の解説などを加えながら構成したものです。
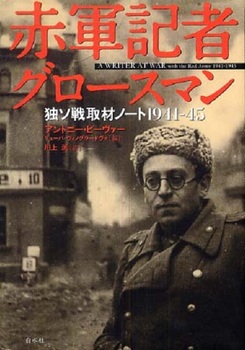
1941年8月、35歳のグロースマンが赤軍の公式機関紙「クラースナヤ・ズヴェズダー」紙の
記者として最初に向かうは、空爆に晒されている白ロシアのゴーメリです。
ちなみに「ズヴェズダー」の意味は「星」ですね。これは現名古屋グランパスの監督
"ピクシー"ストイコヴィッチの心のクラブ、「レッドスター」がセルヴィア語で
「ツルヴェナ・ズヴェズダ」って言うんで知ってます。「クラースナヤ」は・・、わかりません。。
左腕を怪我した兵士・・。戦闘を回避するための「自傷行為」であり、
このような連中はNKVD特務部の手によって即決処刑です。
そして状況は悪化。ドイツ中央軍集団のグデーリアン率いる第2装甲集団が一路南下。
50万人と言われる大敗北「キエフ大包囲」の危機に、グロースマンはなんとか脱出に成功します。
2C20E.Front201941.jpg)
翌月には生まれ故郷のウクライナへ。母親は戦火の中で行方知れず・・。
スターリンのクラーク撲滅と農業強制集団化政策で大飢饉の被害を受けてきたウクライナ人は
ドイツ軍を解放者として歓迎し、ウクライナ人補助警官が母親らも含むユダヤ人の一斉逮捕と
大量虐殺に手を貸したことを知ります。
オリョールへ戻った彼ですが、ここにも悪魔のようなグデーリアン戦車軍団が迫ります。
本書では特にグデーリアン自身が登場するわけではありませんが、
グロースマンの行く先々に現れるグデーリアンと、逃げるグロースマン・・という関係です。

年が明けるとグロースマンの配属先はハリコフ方面へ。
対戦相手は急死したライヒェナウの後任にパウルスが着任したばかりのドイツ第6軍です。
グロースマンは書き記します。
「厳しい寒さ。無傷のドイツ兵の死体。我が軍ではなく、酷寒に殺されたのだ。
兵士らが面白半分にそれらの凍死体を立たせたり、四つん這いにさせたり、
走るような恰好にしたりして、風変わりな幻想的な群像をつくる」
以前に紹介した ↓ の写真もそのような仕業なんでしょうかね。

面白かったのはクルスクには世界最大級の異常磁域があるそうで、
これがカチューシャ・ロケットにいたずらをして、味方最前線に着弾した・・というものです。
そして「クラースナヤ・ズヴェズダー」紙に中編も連載し、
前線の将兵からも人気を博するようになったグロースマン。
夏に向かうのはスターリングラード・・。またしてもパウルスの第6軍が相手です。

8月23日と翌日に行われたドイツ第16装甲師団との激戦。
防衛する高射砲部隊はほとんどが地元の女子高生ですが、驚くべき奮戦を見せ、
掩蔽壕に入れとの命令も聞き入れずに、真正面からドイツ戦車と対決し、
37の砲座が戦車砲ですべて破壊されるまで、第16装甲師団の進撃を食い止めた・・ということです。
すげ~なぁ。。。これだけで映画になりそうですね。
あのルーデルも「急降下爆撃」で、女性のみで編成された高射砲部隊・・と触れてました。。
この中盤のスターリングラード戦はページ数も多く、本書の中心部分です。
確か、著者ビーヴァーの「スターリングラード」もこのグロースマンを参考文献にしてたような。。
また1951年に、このグロースマンのスターリングラードが翻訳されているようです。
ここでも「自傷行為」 ⇒ 「NKVD特務部の即決処刑」が紹介されますが、かなり特殊な例です。
処刑隊がアルコールのせいか銃殺しそこね、穴に埋められた死刑囚が自力で這い出し、
中隊に戻ってきた・・という話です。
この彼の運命は・・・、再度処刑・・。

そしてやっぱり登場のヴァシーリ・ザイツェフ。映画「スターリングラード」のジュート・ロウですね。
当時、狙撃手の手柄はサッカー選手なみに喧伝され、
各師団がそれぞれのスターを自慢していたそうで、その結果、
チュイコフ将軍をも巻き込んだ誇大宣伝競争となって、ザイツェフがドイツ兵225人を殺した・・
ということになったとしています。
素性不明のケーニッヒ少佐なる人物との因縁の決闘も、チュイコフが回想録で大げさに書きたて、
ザイツェフが書いた(とされる)回想録も、数日間に渡る決闘としてスリリングに描かれているとして、
著者ビーヴァーはザイツェフの戦果にかなり否定的です。
そのかわり、グロースマンが取材した8日間で40名を殺した狙撃手との話は
生々しくて興味深いものでした。

若い女性衛生兵の勇敢さは、全員の尊敬の的であったようで、第62軍の衛生中隊は
大多数がスターリングラードの高校生とその卒業生です。
そんな彼女たちにもグロースマンは取材します。
昼間には負傷兵は運ばないという娘は、仲間の衛生兵が頭を打ち抜かれたことを挙げ、
戦闘の1日目で2人死に、18名いた衛生兵もいまでは3人だけ・・という過酷な状況・・。
「砲火の元で水を飲ませ、食べさせ、包帯を巻き、いつの間にか兵隊より頑張るようになって
ハッパを掛けることも・・。だけど夜には震えるほど怖くなって、
あぁ、家に帰れたらいいのになぁ・・なんて思うの」
まさに、<生>戦争は女の顔をしていない・・・ですね。

「天王星作戦」のヘビー級のパンチをまともに食らったルーマニア兵は、銃を棄てて
「アントネスクはもうお手上げ!」と叫びますが、投降しても、その場で銃殺・・。
ルーマニア兵を信用しないドイツ兵は対峙する赤軍兵に向かって
「おーい、ルーマニア兵とウズベク兵を交換しようぜ」と冗談で叫んでいたという話もありました。
包囲された第6軍には噂も流れます。「ヒトラーがピトムニク飛行場までやって来て、
『頑張れ。余が自ら軍を率いて救出しに行く』と語った。しかも彼は伍長の軍服を着ていた・・」

1943年夏のクルスク大戦車戦も取材するグロースマン。
真正面からティーガー戦車を狙って45㎜砲を発射しても砲弾は跳ね返され、
正気を失ってティーガーの下に身を投じた照準手・・、
片足を負傷し、片手をもぎ取られた中尉の指揮で撃退したものの、
不自由な身体で生きることを望まない彼は、拳銃自殺を遂げた。。

グロースマンは遂にウクライナに戻ってきます。しかしそこにはユダヤ人の姿はありません。
そしてこのホロコーストの記事は当局には歓迎されず、
「特殊な犠牲者」を認めないスターリンによって、ホロコーストの犠牲者は「ソ連人民」と定義。。
これはソ連の反ユダヤ主義、ウクライナ人によるユダヤ人迫害の事実も具合が悪いわけです。
第65軍には荷車を牽く1頭のラクダ・・その名は「クズネーチク」と言い、
「戦傷者名誉賞」を3つ、「スターリングラード防衛戦功労賞」も授かってる有名なラクダです。
そして彼らはこのラクダと共に、一路、ベルリンを目指します。

30ページにわたって書かれた「トレブリンカ」絶滅収容所の歴史と、その凄まじさは
以前に「トレブリンカ」を読んで知ってはいたものの、本書の書きっぷりは力強く、
読んでいて思わず「生唾ゴクリ・・」となるほどでした。
これは双方の関係者や目撃者からグロースマンが聞き取った話をまとめたようですが、
クルト・フランツ所長と、その部下たちの残虐性は衝撃的なほどです。
この「トレブリンカの地獄」という記事は、ニュルンベルク裁判でも引用されたそうで、
例えだけでも、ここでは書く気が起きませんね。

チュイコフ将軍の第8親衛軍に同行し、ドイツ国境を越えたグロースマンですが、
突如、兵士の暴虐ぶりを見せつけられます。
それはもちろん略奪とレイプ・・。開け放たれた窓から女性の悲鳴・・。
収容所から解放されたソ連女性も特派員の部屋に避難しますが、
同僚の特派員が欲望に負けて、この部屋でも悲鳴が・・。

ソ連が受けた損害を補てんするために部隊に随行する「貴金属類没収委員会」は、
先々で従順なドイツ人に金庫を開けさせますが、
一般兵士も、我も・・とばかりに鹵獲パンツァーファウストで金庫を一撃・・。
その結果は、金庫も中身もメチャクチャです。。
戦いが収まったばかりの1945年5月2日のベルリンの様子。
「ライヒスタークで最期まで戦ったドイツ軍兵士たちは、ほとんどが手榴弾と
自動小銃を握りしめたまま、戦いながらの死・・。
道路の泥の中に靴を履いた女の子の両足。戦車に蹂躙されたのか、砲弾の直撃を喰らったのか。
子供を連れた兵士は泣き崩れ、若い美人妻はニコニコ笑って亭主を励ましている」

500ページ越えの本書ですが、グロースマンが赤軍の宣伝マシーンのような人物ではなく、
冷静に事実を伝えようとしたこと・・、ですが、もちろんそんなことは不可能であり、
掲載された彼の記事も、編集部によって削られ、追加され・・といじくり回されてしまいます。
そのグロースマンの本音が伺えるのが、この「取材ノート」であって、ビーヴァーの解説や説明が
状況をわかりやすくしています。敵味方ではなく、人間の常識と良心を基準に
戦争を見つめるグロースマンの視点は好感が持てるものでした。
これで心置きなく「ノルマンディー上陸作戦1944」に突入できるかと思いきや、
今年2月に「スペイン内戦 -1936-1939-」も出てましたね・・。
これも「ゲルニカ」やら「コンドル軍団」といった話があるんだと思うと、無視できないんですよね。
アントニー・ビーヴァー著の「赤軍記者グロースマン」を読破しました。
過去に「スターリングラード」や「ベルリン陥落 1945」、そして「ベルリン終戦日記」と紹介している
自分の好きな英国の著者、アントニー・ビーヴァーの上下巻の大作、
「ノルマンディー上陸作戦1944」が夏に発売され、「お~、コレ読みたいなぁ・・」と思ったものの、
そういえばグロースマン読んでなかった・・ということに気づきました。
2007年発刊の本書は、ウクライナ生まれのユダヤ人作家グロースマンが、
独ソ戦勃発とともに従軍記者として最前線で見聞きし、それをメモしたノートを中心に、
彼が緒戦の「キエフ大包囲」から「スターリングラード」を経て、ベルリンに至るまでを
著者ビーヴァーの戦局の解説などを加えながら構成したものです。
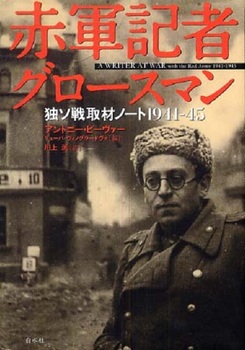
1941年8月、35歳のグロースマンが赤軍の公式機関紙「クラースナヤ・ズヴェズダー」紙の
記者として最初に向かうは、空爆に晒されている白ロシアのゴーメリです。
ちなみに「ズヴェズダー」の意味は「星」ですね。これは現名古屋グランパスの監督
"ピクシー"ストイコヴィッチの心のクラブ、「レッドスター」がセルヴィア語で
「ツルヴェナ・ズヴェズダ」って言うんで知ってます。「クラースナヤ」は・・、わかりません。。
左腕を怪我した兵士・・。戦闘を回避するための「自傷行為」であり、
このような連中はNKVD特務部の手によって即決処刑です。
そして状況は悪化。ドイツ中央軍集団のグデーリアン率いる第2装甲集団が一路南下。
50万人と言われる大敗北「キエフ大包囲」の危機に、グロースマンはなんとか脱出に成功します。
2C20E.Front201941.jpg)
翌月には生まれ故郷のウクライナへ。母親は戦火の中で行方知れず・・。
スターリンのクラーク撲滅と農業強制集団化政策で大飢饉の被害を受けてきたウクライナ人は
ドイツ軍を解放者として歓迎し、ウクライナ人補助警官が母親らも含むユダヤ人の一斉逮捕と
大量虐殺に手を貸したことを知ります。
オリョールへ戻った彼ですが、ここにも悪魔のようなグデーリアン戦車軍団が迫ります。
本書では特にグデーリアン自身が登場するわけではありませんが、
グロースマンの行く先々に現れるグデーリアンと、逃げるグロースマン・・という関係です。

年が明けるとグロースマンの配属先はハリコフ方面へ。
対戦相手は急死したライヒェナウの後任にパウルスが着任したばかりのドイツ第6軍です。
グロースマンは書き記します。
「厳しい寒さ。無傷のドイツ兵の死体。我が軍ではなく、酷寒に殺されたのだ。
兵士らが面白半分にそれらの凍死体を立たせたり、四つん這いにさせたり、
走るような恰好にしたりして、風変わりな幻想的な群像をつくる」
以前に紹介した ↓ の写真もそのような仕業なんでしょうかね。

面白かったのはクルスクには世界最大級の異常磁域があるそうで、
これがカチューシャ・ロケットにいたずらをして、味方最前線に着弾した・・というものです。
そして「クラースナヤ・ズヴェズダー」紙に中編も連載し、
前線の将兵からも人気を博するようになったグロースマン。
夏に向かうのはスターリングラード・・。またしてもパウルスの第6軍が相手です。

8月23日と翌日に行われたドイツ第16装甲師団との激戦。
防衛する高射砲部隊はほとんどが地元の女子高生ですが、驚くべき奮戦を見せ、
掩蔽壕に入れとの命令も聞き入れずに、真正面からドイツ戦車と対決し、
37の砲座が戦車砲ですべて破壊されるまで、第16装甲師団の進撃を食い止めた・・ということです。
すげ~なぁ。。。これだけで映画になりそうですね。
あのルーデルも「急降下爆撃」で、女性のみで編成された高射砲部隊・・と触れてました。。
この中盤のスターリングラード戦はページ数も多く、本書の中心部分です。
確か、著者ビーヴァーの「スターリングラード」もこのグロースマンを参考文献にしてたような。。
また1951年に、このグロースマンのスターリングラードが翻訳されているようです。
ここでも「自傷行為」 ⇒ 「NKVD特務部の即決処刑」が紹介されますが、かなり特殊な例です。
処刑隊がアルコールのせいか銃殺しそこね、穴に埋められた死刑囚が自力で這い出し、
中隊に戻ってきた・・という話です。
この彼の運命は・・・、再度処刑・・。

そしてやっぱり登場のヴァシーリ・ザイツェフ。映画「スターリングラード」のジュート・ロウですね。
当時、狙撃手の手柄はサッカー選手なみに喧伝され、
各師団がそれぞれのスターを自慢していたそうで、その結果、
チュイコフ将軍をも巻き込んだ誇大宣伝競争となって、ザイツェフがドイツ兵225人を殺した・・
ということになったとしています。
素性不明のケーニッヒ少佐なる人物との因縁の決闘も、チュイコフが回想録で大げさに書きたて、
ザイツェフが書いた(とされる)回想録も、数日間に渡る決闘としてスリリングに描かれているとして、
著者ビーヴァーはザイツェフの戦果にかなり否定的です。
そのかわり、グロースマンが取材した8日間で40名を殺した狙撃手との話は
生々しくて興味深いものでした。

若い女性衛生兵の勇敢さは、全員の尊敬の的であったようで、第62軍の衛生中隊は
大多数がスターリングラードの高校生とその卒業生です。
そんな彼女たちにもグロースマンは取材します。
昼間には負傷兵は運ばないという娘は、仲間の衛生兵が頭を打ち抜かれたことを挙げ、
戦闘の1日目で2人死に、18名いた衛生兵もいまでは3人だけ・・という過酷な状況・・。
「砲火の元で水を飲ませ、食べさせ、包帯を巻き、いつの間にか兵隊より頑張るようになって
ハッパを掛けることも・・。だけど夜には震えるほど怖くなって、
あぁ、家に帰れたらいいのになぁ・・なんて思うの」
まさに、<生>戦争は女の顔をしていない・・・ですね。

「天王星作戦」のヘビー級のパンチをまともに食らったルーマニア兵は、銃を棄てて
「アントネスクはもうお手上げ!」と叫びますが、投降しても、その場で銃殺・・。
ルーマニア兵を信用しないドイツ兵は対峙する赤軍兵に向かって
「おーい、ルーマニア兵とウズベク兵を交換しようぜ」と冗談で叫んでいたという話もありました。
包囲された第6軍には噂も流れます。「ヒトラーがピトムニク飛行場までやって来て、
『頑張れ。余が自ら軍を率いて救出しに行く』と語った。しかも彼は伍長の軍服を着ていた・・」

1943年夏のクルスク大戦車戦も取材するグロースマン。
真正面からティーガー戦車を狙って45㎜砲を発射しても砲弾は跳ね返され、
正気を失ってティーガーの下に身を投じた照準手・・、
片足を負傷し、片手をもぎ取られた中尉の指揮で撃退したものの、
不自由な身体で生きることを望まない彼は、拳銃自殺を遂げた。。

グロースマンは遂にウクライナに戻ってきます。しかしそこにはユダヤ人の姿はありません。
そしてこのホロコーストの記事は当局には歓迎されず、
「特殊な犠牲者」を認めないスターリンによって、ホロコーストの犠牲者は「ソ連人民」と定義。。
これはソ連の反ユダヤ主義、ウクライナ人によるユダヤ人迫害の事実も具合が悪いわけです。
第65軍には荷車を牽く1頭のラクダ・・その名は「クズネーチク」と言い、
「戦傷者名誉賞」を3つ、「スターリングラード防衛戦功労賞」も授かってる有名なラクダです。
そして彼らはこのラクダと共に、一路、ベルリンを目指します。

30ページにわたって書かれた「トレブリンカ」絶滅収容所の歴史と、その凄まじさは
以前に「トレブリンカ」を読んで知ってはいたものの、本書の書きっぷりは力強く、
読んでいて思わず「生唾ゴクリ・・」となるほどでした。
これは双方の関係者や目撃者からグロースマンが聞き取った話をまとめたようですが、
クルト・フランツ所長と、その部下たちの残虐性は衝撃的なほどです。
この「トレブリンカの地獄」という記事は、ニュルンベルク裁判でも引用されたそうで、
例えだけでも、ここでは書く気が起きませんね。

チュイコフ将軍の第8親衛軍に同行し、ドイツ国境を越えたグロースマンですが、
突如、兵士の暴虐ぶりを見せつけられます。
それはもちろん略奪とレイプ・・。開け放たれた窓から女性の悲鳴・・。
収容所から解放されたソ連女性も特派員の部屋に避難しますが、
同僚の特派員が欲望に負けて、この部屋でも悲鳴が・・。

ソ連が受けた損害を補てんするために部隊に随行する「貴金属類没収委員会」は、
先々で従順なドイツ人に金庫を開けさせますが、
一般兵士も、我も・・とばかりに鹵獲パンツァーファウストで金庫を一撃・・。
その結果は、金庫も中身もメチャクチャです。。
戦いが収まったばかりの1945年5月2日のベルリンの様子。
「ライヒスタークで最期まで戦ったドイツ軍兵士たちは、ほとんどが手榴弾と
自動小銃を握りしめたまま、戦いながらの死・・。
道路の泥の中に靴を履いた女の子の両足。戦車に蹂躙されたのか、砲弾の直撃を喰らったのか。
子供を連れた兵士は泣き崩れ、若い美人妻はニコニコ笑って亭主を励ましている」

500ページ越えの本書ですが、グロースマンが赤軍の宣伝マシーンのような人物ではなく、
冷静に事実を伝えようとしたこと・・、ですが、もちろんそんなことは不可能であり、
掲載された彼の記事も、編集部によって削られ、追加され・・といじくり回されてしまいます。
そのグロースマンの本音が伺えるのが、この「取材ノート」であって、ビーヴァーの解説や説明が
状況をわかりやすくしています。敵味方ではなく、人間の常識と良心を基準に
戦争を見つめるグロースマンの視点は好感が持てるものでした。
これで心置きなく「ノルマンディー上陸作戦1944」に突入できるかと思いきや、
今年2月に「スペイン内戦 -1936-1939-」も出てましたね・・。
これも「ゲルニカ」やら「コンドル軍団」といった話があるんだと思うと、無視できないんですよね。
2011-10-11 07:04
nice!(1)
コメント(8)
トラックバック(0)




これは名作でしたね。
ちなみにクラスナーヤは、赤い、さらに美しいという古語。
赤い星は赤軍機関誌です
「クラスヌーイ・オクチャブリ」はレッドオクとバーになります。
本書にも出てくるスターリン御用詩人、エレンブルグの有名なアジ文章
「赤軍兵士諸君、復讐せよ。ドイツ人に無実なものはいない。破壊し焼尽せ、女は諸君らの戦利品である」も赤い星にのったと。つまり、グロースマンに出てくる理性と、エレンブルグスターリン狂気の双方が、ソ連にもあったと。
グロースマンは、そんな中でも、人間らしさを残した。彼が迫害されたのも、当然かと。あと、ソ連が続いたのも、グロースマン後半のトーン、勝利の歓喜が、党への信頼を作ってしまったのかと。
ビーバー、今、歴史かランキングでトップですね。
by 石井孝明 (2011-10-12 09:32)
石井さん、こんにちわ。
「クラースナヤ」の解説、ありがとうございました。
>グロースマンは、そんな中でも、人間らしさを残した。彼が迫害されたのも、当然かと。
そうですね。本書に書かれていたグロースマンのその後・・は、あえて端折りましたが、やっぱり書いておくべきだったかなぁ・・と。。
歴史家ランキングっていうのは初めて知りました。
by ヴィトゲンシュタイン (2011-10-12 12:42)
すみません、歴史家らんきんぐは、「私(石井)の」という意味です 笑
by 石井孝明 (2011-10-12 13:33)
なはは、そうでしたか・・。検索しちゃいました。。。
by ヴィトゲンシュタイン (2011-10-12 19:04)
こんばんは~
最近ロムってばかりいました。この記事もよんでいたのですが、それ以来この内容が頭の中でずっとぐるぐるしています。。。
頭のまともなジャーナリストって、結局苦労するんだなあ、(今の日本の状態と重なってしょうがないです)とか、敵兵の死体をもてあそぶって、戦争中は皆おかしくなっちゃうんだなあとか、台所に立ちながらでもこの記事の事を考えています。
あの国では割と最近でも政府批判のジャーナリストが暗殺されてたりとか、まあ、記者さんというのは命がけですよね、例え戦場でなくとも。
すごく気になりましたのでいつかよんで見たいです。
by IZM (2011-10-20 04:27)
IZMさん。おはようございます。
>あの国では割と最近でも政府批判のジャーナリストが暗殺されてたりとか
そうなんですよね。この「独破戦線」ではジャンルが違うので紹介していませんが、「リトビネンコ暗殺」とか、チェチェン関係とか、何冊か読んでいます。△ーチン体制は興味深いですからね。
暗殺された女性記者アンナ・ポリトコフスカヤの「チェチェン やめられない戦争」と「ロシアン・ダイアリー―暗殺された女性記者の取材手帳」もコッソリ読んでみるつもりです。
by ヴィトゲンシュタイン (2011-10-20 06:44)
おお~、やっぱり気になりますよね、あのへんの事情は。
しかし他の本をよむ余裕もちゃんとあるのですね!本当に書物がお好きなのですね~。
by IZM (2011-10-20 16:59)
そう、気になります。まさに現代の・・??
>しかし他の本をよむ余裕もちゃんとあるのですね!
コレはあんまりないんですよ。怒られない程度に番外編で登場しますが、本棚に眠ったままが多いですね。
そのうちにコッソリと別のBlogもやってるかも・・。
by ヴィトゲンシュタイン (2011-10-20 20:49)