焦土作戦 -独ソ戦史- (下) [戦記]
ど~も。ヴィトゲンシュタインです。
パウル・カレル著の「焦土作戦 (下)」を再度読破しました。
この下巻ではいよいよドニエプル河で戦線を安定させたドイツ軍に対する
ソ連軍の攻勢が始まります。
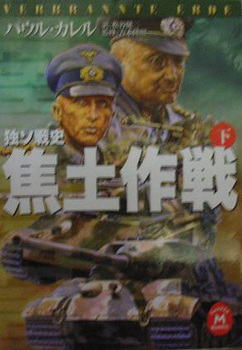
第1ウクライナ軍集団(方面軍)のバトゥーチンを中心に、
またもソ連軍がドイツ南方軍集団に襲い掛かり、再度マンシュタインの防衛戦、
今度もヒトラーを敵にまわしながらの戦いです。
ちなみにバトゥーチンはこの「焦土作戦」におけるソ連側の主役と言って良いでしょう。

ニコポリ橋頭堡の防衛戦ではフェルディナンド・シェルナー山岳兵大将が登場し、
彼の勇気、厳しさ、決断力、戦術能力、そして有名な「鉄の規律」について
紹介されています。
この人はヒトラーの人望が厚かったり、脱走兵を容赦なく街灯に吊るしたりしたことで
賛否両論ある将軍ですが、本書では、その戦いっぷりについては好意的です。

そしてこの「焦土作戦」全般を通しての個人的なお気に入り「チェルカッスィ」は
何度読んでも面白いですね。
初めて読んだ時にも、なぜか特別に印象深い戦い、というか
スターリングラード以外にあまり知らなかった包囲戦、そして救援/脱出という
ドラマティックさがあるからでしょうか。
あのボリュームたっぷりな「チェルカッシィ包囲網突破戦」を読むまでにも、
何度かこの章だけは読み直した記憶があります。

60ページ程度のこの章は、とにかく包囲陣内の複数師団の絶望的な様子と
救出に向かう強烈な装甲部隊にソ連軍の執拗な防衛戦、
この救出作戦を指揮するマンシュタインとソ連側、果ては味方との駆け引き、
そして脱出を決断する、ここでのパウルス元帥であるシュテンマーマン将軍と
その壮絶で手に汗握る脱出行・・。
これらが、簡潔かつ的確に語られ、最初読んだときには
いったいどんな結末を迎えるのか・・とドキドキしたものです。

続く第1ウクライナ軍集団の攻撃の前にフーベ将軍の第1装甲軍が包囲され、
西の第4装甲軍と連絡をつけるべく、移動しながらの攻防も印象的です。
バトゥーチンがウクライナの匪賊に討たれ、後には死亡したため、
このソ連最強の軍集団はエースのジューコフが率いることになります。
しかし、見事ドイツ軍は退却と連絡に成功し、フーベもヒトラーの手により
宝剣付き柏葉騎士十字章を授かりますが、乗機がベルヒテスガーデン近郊で墜落。
さらには「作戦の時期は終わった」との理由で、マンシュタインも罷免されることになります。

クリミアまでも失ったドイツ軍は、1944年6月、西側連合軍の
ノルマンディ上陸、そして東部戦線ではソ連のバグラチオン作戦が発動され、
モーデルの中央軍集団が崩壊していくところで本書は終わります。
途中、マンシュタインの副官であったシュタールベルクが大した意味もなく
突然に出てくるあたりは、さすがカレルです。驚きました。
初版当時(1972年)の松谷健二氏の「訳者あとがき」が載せられていて
本書に続く「ベルリン最終戦」の執筆状況について書かれています
(残念ながらカレル氏は完成させることなく他界)。

また本文にもちょくちょく登場のソ連諜報の責任者、ラインハルト・ゲーレンの
爆弾発言とされる「マルティン・ボルマンが実はソ連のスパイであり、
ベルリン陥落寸前にソ連に亡命した」という話を引用しています。
この話はあまり知らなかったのですが、翻訳されている「ゲーレン」の本に
書いてあるんでしょうかね?
まぁ。ボルマンについては今でも死体が発見されたとか(コレも結構あやしい?)
いろいろ話があるので、なんとも言えませんが
今度、スパイ関係のものを読んでみようと思います。
今日はちゃんと「独破リスト」を更新しておきます・・。
パウル・カレル著の「焦土作戦 (下)」を再度読破しました。
この下巻ではいよいよドニエプル河で戦線を安定させたドイツ軍に対する
ソ連軍の攻勢が始まります。
第1ウクライナ軍集団(方面軍)のバトゥーチンを中心に、
またもソ連軍がドイツ南方軍集団に襲い掛かり、再度マンシュタインの防衛戦、
今度もヒトラーを敵にまわしながらの戦いです。
ちなみにバトゥーチンはこの「焦土作戦」におけるソ連側の主役と言って良いでしょう。

ニコポリ橋頭堡の防衛戦ではフェルディナンド・シェルナー山岳兵大将が登場し、
彼の勇気、厳しさ、決断力、戦術能力、そして有名な「鉄の規律」について
紹介されています。
この人はヒトラーの人望が厚かったり、脱走兵を容赦なく街灯に吊るしたりしたことで
賛否両論ある将軍ですが、本書では、その戦いっぷりについては好意的です。

そしてこの「焦土作戦」全般を通しての個人的なお気に入り「チェルカッスィ」は
何度読んでも面白いですね。
初めて読んだ時にも、なぜか特別に印象深い戦い、というか
スターリングラード以外にあまり知らなかった包囲戦、そして救援/脱出という
ドラマティックさがあるからでしょうか。
あのボリュームたっぷりな「チェルカッシィ包囲網突破戦」を読むまでにも、
何度かこの章だけは読み直した記憶があります。

60ページ程度のこの章は、とにかく包囲陣内の複数師団の絶望的な様子と
救出に向かう強烈な装甲部隊にソ連軍の執拗な防衛戦、
この救出作戦を指揮するマンシュタインとソ連側、果ては味方との駆け引き、
そして脱出を決断する、ここでのパウルス元帥であるシュテンマーマン将軍と
その壮絶で手に汗握る脱出行・・。
これらが、簡潔かつ的確に語られ、最初読んだときには
いったいどんな結末を迎えるのか・・とドキドキしたものです。

続く第1ウクライナ軍集団の攻撃の前にフーベ将軍の第1装甲軍が包囲され、
西の第4装甲軍と連絡をつけるべく、移動しながらの攻防も印象的です。
バトゥーチンがウクライナの匪賊に討たれ、後には死亡したため、
このソ連最強の軍集団はエースのジューコフが率いることになります。
しかし、見事ドイツ軍は退却と連絡に成功し、フーベもヒトラーの手により
宝剣付き柏葉騎士十字章を授かりますが、乗機がベルヒテスガーデン近郊で墜落。
さらには「作戦の時期は終わった」との理由で、マンシュタインも罷免されることになります。
クリミアまでも失ったドイツ軍は、1944年6月、西側連合軍の
ノルマンディ上陸、そして東部戦線ではソ連のバグラチオン作戦が発動され、
モーデルの中央軍集団が崩壊していくところで本書は終わります。
途中、マンシュタインの副官であったシュタールベルクが大した意味もなく
突然に出てくるあたりは、さすがカレルです。驚きました。
初版当時(1972年)の松谷健二氏の「訳者あとがき」が載せられていて
本書に続く「ベルリン最終戦」の執筆状況について書かれています
(残念ながらカレル氏は完成させることなく他界)。

また本文にもちょくちょく登場のソ連諜報の責任者、ラインハルト・ゲーレンの
爆弾発言とされる「マルティン・ボルマンが実はソ連のスパイであり、
ベルリン陥落寸前にソ連に亡命した」という話を引用しています。
この話はあまり知らなかったのですが、翻訳されている「ゲーレン」の本に
書いてあるんでしょうかね?
まぁ。ボルマンについては今でも死体が発見されたとか(コレも結構あやしい?)
いろいろ話があるので、なんとも言えませんが
今度、スパイ関係のものを読んでみようと思います。
今日はちゃんと「独破リスト」を更新しておきます・・。




読了乙です。
最終巻の相次ぐ包囲、撤退の話。負けにもかかわらず奮闘する独軍
日本人好み?な展開です。その中で光る行動、キロォグラードの
バイエルライン、合理的に行動すればソ連軍と互角に戦えるのに、、
この本のテーゼの見本みたいな話です。
カレル一流の話運び、マンシュタインとジューコフがテーブルを共にしている
かのごとき描写、「ますますけっこう!」読んでるこっちも「けっこう!」と
なってしまいます。
包囲脱出して戦線は安定危機は去った、ジューコフ「独軍いまだ侮りがたし、、」どっちが勝ってるのでしょ?て感じの話はこびですもの。
まあこうでも書かないと悲惨すぎる話の連続ですからね。
高橋さん「武装SS師団写真史」マイナー師団が参考になります。
by グライフ (2010-03-29 09:51)
とっても「けっこう!」なコメントありがとうございます。爆笑しました・・。
「武装SS師団写真史」、おととい神保町で偶然見つけて軽く、立ち読みしました。
神保町へは、ゲーレンとシェレンベルクの本を探しに行ったんですが、
さすがに見つかりませんでしたねぇ。
amazonでは、結構な第2次大戦本を購入しているにもかかわらず、
「武装SS師団写真史」のような大事な本が「おすすめ商品」として反映されません。
まったく困ったもので、その代わり「萌えよ!戦車学校IV型」を1ページ目からすすめられてしまっています。。。
そういうの興味ないんですけどねぇ・・。
by ヴィトゲンシュタイン (2010-03-29 19:14)
>爆弾発言とされる「マルティン・ボルマンが…
確か書いてあったですね、(うろ覚え)でスパイが発信していると思しき謎の電波を調査しようとしたところ「あれはボルマンが総統に許可を得て行っている欺瞞作戦である関わるな」ってことで断念したって経緯でしたか、かなり悔しそうな書き方してた気がしてたんですが。
何しろ読んだのがもう10年以上前なんでそこんとこよろしく。
by アナベル・加トー少佐 (2010-07-02 01:47)