ヒトラーの外交官 -リッベントロップは、なぜ悪魔に仕えたか- [ヒトラーの側近たち]
ど~も。ヴィトゲンシュタインです。
ジョン・ワイツ著の「ヒトラーの外交官」を読破しました。
言わずと知れた第三帝国の外相であったリッベントロップ伝です。
1年半前に購入したものの、なかなか読むキッカケがなく
「クルスクの戦い」で息子の活躍を読んだ勢いでやっとページを開いてみました。
ニュルンベルク裁判の拘留中に本人の書いた回願録をベースに、
ヒトラーの通訳も務めたシュミットの発言などで裏付けしているというのが基本構成です。
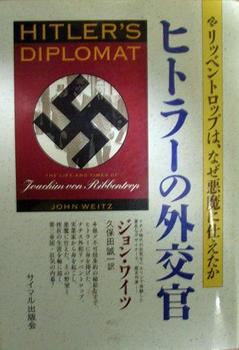
まずは彼の生い立ちからです。
「フォン」という貴族の称号をおばさんの養子になることで買ったということや
それよりも有名なシャンパン業者という経歴の紹介に続き、
台頭してきたヒトラーの上流社会や外国人に疎いところを指南するチャンスを得るものの、
逆にヒトラーの影響をモロに受けてしまうことに・・。
それなりにヒトラーには重宝されますが、入党も遅く、古参のナチ党員から疎んじられることからか
親衛隊に入隊して頑張っている所も大いにアピールしようとします。
嫁さんがなかなかのもので、常に尻に引かれていると周りからも思われていたようで、
ゲッベルスやゲーリングは笑いのネタにもしている感じです。

ナチス政権発足当初から外相を務めていたノイラートとライバル関係となりますが、
なかなかその座は得られず、「大使」として英国などとの交渉に挑みます。
本人は定年の近いノイラートの後任は間違いなく自分であると言い触らして
ヒトラーから叱責を受け、すっかり落ち込んでしまい、
ゲーリングやゲッベルス、ローゼンベルクが次期外相候補に挙げられたそうです。
最終的には空軍や宣伝といった本職に専念すべしとのヒトラーの考えから
めでたく外相に就任するのでした。

防諜部長官のヴァルター・シェレンベルクがパリの愛人、ココ・シャネルのもとから
呼び戻され・・・という話も出てきます。
この本の記述だけでは本当かどうかはわかりませんが、割と知られた話である
ココ・シャネルの愛人のナチ高官というがシェレンベルクだったというのは初めて知りました。
下世話な話ですが、30歳そこそこのシェレンベルクに対してココ・シャネルは50台後半ですね。

シェレンベルクが呼び戻された理由はウィンザー公に関する有名な策謀によるものですが、
ちょっと調べてみると、この話は「鷲は舞い降りた」のジャック・ヒギンズが別名で
「ウィンザー公掠奪」というシェレンベルクが主人公の小説を書いてるんですね。
「鷲は飛び立った」にも登場しているそうですが、これはまったく記憶にありません。。
シェレンベルク本人も「秘密機関長の手記」という、まるで密輸船ものみたいな
邦題のついた本を出していました。
これはちょっと古い本で、さすがに売っていません。
主役であるはずのリッベントロップが悲しいほどに面白味のない人物なので、
ついつい、このような個性的な脇役に興味がいってしまいました。

「親衛隊大将(分隊長)」とか、当時大尉の階級のスコルツェニーが「大佐」だったり
ロンメルが「戦車兵出身」などという意味不明な記述も散見されます。
著者はこの手の部分は得意じゃないのかも知れませんが、
ひょっとするとただの誤訳なのかも・・。
また、ヒトラー発祥国であるオーストリアがドイツとの人口比率からして、
SS隊員が多かったと分析しており、特に「特別行動隊=アインザッツグルッペン」や
「髑髏部隊」、即ち収容所の看守が多かったということや
悪名高いアイヒマンやカルテンブルンナーなどがオーストリア人であることを挙げて、
暗にドイツ人より、残虐な国民であるかのように解説しています。。
これは同じSS隊員でも前線部隊の兵士はある程度マトモで、
強制収容所の看守は極悪非道な人間という安直な発想であると思いますね。

リッベントロップのハイライトとも言える「独ソ不可侵条約」締結から、
それを破棄してしまった1941年の「バルバロッサ作戦」以降の彼の活躍は
まったくと言っていいほどなくなってしまいます。
その後の終戦まで、なぜ彼が外相の地位を維持し続けることが出来たのかに
興味があったんですが、特にそれには触れられず、
ここからはあっという間にこの本も終わってしまいます。

結局、大戦中は外相としてするべきこともなく、ヒトラーもイエスマンである彼を
解任する必要も無かったということなのでしょう。
この本を読むまで、ニュルンベルクで絞首刑となった彼の犯罪性とはなにか?
良くわからずにいましたが、読み終えても結局良くわからないままです。。。
成功して認められたいと思う、若干気の弱いどこにでもいるような人間が
その地位を失うことを怖れて、最後までヒトラーに追随してしまった・・
ということだけなのでしょうか。
ジョン・ワイツ著の「ヒトラーの外交官」を読破しました。
言わずと知れた第三帝国の外相であったリッベントロップ伝です。
1年半前に購入したものの、なかなか読むキッカケがなく
「クルスクの戦い」で息子の活躍を読んだ勢いでやっとページを開いてみました。
ニュルンベルク裁判の拘留中に本人の書いた回願録をベースに、
ヒトラーの通訳も務めたシュミットの発言などで裏付けしているというのが基本構成です。
まずは彼の生い立ちからです。
「フォン」という貴族の称号をおばさんの養子になることで買ったということや
それよりも有名なシャンパン業者という経歴の紹介に続き、
台頭してきたヒトラーの上流社会や外国人に疎いところを指南するチャンスを得るものの、
逆にヒトラーの影響をモロに受けてしまうことに・・。
それなりにヒトラーには重宝されますが、入党も遅く、古参のナチ党員から疎んじられることからか
親衛隊に入隊して頑張っている所も大いにアピールしようとします。
嫁さんがなかなかのもので、常に尻に引かれていると周りからも思われていたようで、
ゲッベルスやゲーリングは笑いのネタにもしている感じです。

ナチス政権発足当初から外相を務めていたノイラートとライバル関係となりますが、
なかなかその座は得られず、「大使」として英国などとの交渉に挑みます。
本人は定年の近いノイラートの後任は間違いなく自分であると言い触らして
ヒトラーから叱責を受け、すっかり落ち込んでしまい、
ゲーリングやゲッベルス、ローゼンベルクが次期外相候補に挙げられたそうです。
最終的には空軍や宣伝といった本職に専念すべしとのヒトラーの考えから
めでたく外相に就任するのでした。

防諜部長官のヴァルター・シェレンベルクがパリの愛人、ココ・シャネルのもとから
呼び戻され・・・という話も出てきます。
この本の記述だけでは本当かどうかはわかりませんが、割と知られた話である
ココ・シャネルの愛人のナチ高官というがシェレンベルクだったというのは初めて知りました。
下世話な話ですが、30歳そこそこのシェレンベルクに対してココ・シャネルは50台後半ですね。

シェレンベルクが呼び戻された理由はウィンザー公に関する有名な策謀によるものですが、
ちょっと調べてみると、この話は「鷲は舞い降りた」のジャック・ヒギンズが別名で
「ウィンザー公掠奪」というシェレンベルクが主人公の小説を書いてるんですね。
「鷲は飛び立った」にも登場しているそうですが、これはまったく記憶にありません。。
シェレンベルク本人も「秘密機関長の手記」という、まるで密輸船ものみたいな
邦題のついた本を出していました。
これはちょっと古い本で、さすがに売っていません。
主役であるはずのリッベントロップが悲しいほどに面白味のない人物なので、
ついつい、このような個性的な脇役に興味がいってしまいました。

「親衛隊大将(分隊長)」とか、当時大尉の階級のスコルツェニーが「大佐」だったり
ロンメルが「戦車兵出身」などという意味不明な記述も散見されます。
著者はこの手の部分は得意じゃないのかも知れませんが、
ひょっとするとただの誤訳なのかも・・。
また、ヒトラー発祥国であるオーストリアがドイツとの人口比率からして、
SS隊員が多かったと分析しており、特に「特別行動隊=アインザッツグルッペン」や
「髑髏部隊」、即ち収容所の看守が多かったということや
悪名高いアイヒマンやカルテンブルンナーなどがオーストリア人であることを挙げて、
暗にドイツ人より、残虐な国民であるかのように解説しています。。
これは同じSS隊員でも前線部隊の兵士はある程度マトモで、
強制収容所の看守は極悪非道な人間という安直な発想であると思いますね。
リッベントロップのハイライトとも言える「独ソ不可侵条約」締結から、
それを破棄してしまった1941年の「バルバロッサ作戦」以降の彼の活躍は
まったくと言っていいほどなくなってしまいます。
その後の終戦まで、なぜ彼が外相の地位を維持し続けることが出来たのかに
興味があったんですが、特にそれには触れられず、
ここからはあっという間にこの本も終わってしまいます。

結局、大戦中は外相としてするべきこともなく、ヒトラーもイエスマンである彼を
解任する必要も無かったということなのでしょう。
この本を読むまで、ニュルンベルクで絞首刑となった彼の犯罪性とはなにか?
良くわからずにいましたが、読み終えても結局良くわからないままです。。。
成功して認められたいと思う、若干気の弱いどこにでもいるような人間が
その地位を失うことを怖れて、最後までヒトラーに追随してしまった・・
ということだけなのでしょうか。




お邪魔します。
シェレンベルクは、シャネルに会いにパリに行ったことはありません。
シャネルがシェレンベルクに会いにベルリンへ行ったことはありますが。
シャネルの愛人は、シェレンベルクの部下だったと言われる”スパッツ”ことハンス・フォン・ディンクラージです。彼は戦中~戦後しばらくは、シャネルの愛人でした。彼にしてもシェレンベルクより年上でしたが、シャネルよりは10歳以上年下です。
by M.不破 (2009-11-28 04:19)
ど~も。M.不破さん。
コメント&情報ありがとうございます。
自分もこの本を読むまでは、シャネルの愛人はご指摘のとおりだと思っていました。その後、調べたところでも明確にシェレンベルクであるという確証は得られず・・。まぁ、本のブログなので、この本に書かれている、シェレンベルクという話を自分が初めて聞いたのは事実なので、グレーな表現に押さえたつもりです。
でも、こうゆうコメントも大歓迎ですよ。
by ヴィトゲンシュタイン (2009-11-28 05:14)
はじめまして。私は日本近現代史を研究している者です。ちなみに卒論は広田弘毅なので、貴サイトに大変興味を持ちました。
リッベントロップといえば、私の専門(?)では日独防共協定に関係しますね。戦後の東京裁判で広田が絞首刑となった理由の一つですが、この時のドイツ側の交渉相手でした(日本側は駐独大使武官の陸軍軍人・大島浩)。恥ずかしながら、世界史にはあまり詳しくない私ですが、これを機に勉強したいと思います。
by 第一機動艦隊司令長官 (2014-10-05 23:35)
ど~も、第一機動艦隊司令長官どの!
広田弘毅といえば、今年、「東京裁判」を読んだ際にこのBlogでも紹介しました。ボクはその時に詳しく知った次第です。
http://ona.blog.so-net.ne.jp/2014-01-11
このBlogは現在更新していませんが、当該記事のような過去記事でもお役に立てれば幸いです。
コメント、ありがとうございました。
by ヴィトゲンシュタイン (2014-10-07 11:50)