戦場のピアニスト [戦争映画の本]
ど~も。ヴィトゲンシュタインです。
ウワディスワフ・シュピルマン著の「戦場のピアニスト」を読破しました。
ロマン・ポランスキー監督の映画でも有名な一冊です。
公開当時に観に行きました。だいぶ原作に忠実な映画だったんですね。
読んでいるうちに、当時観た映像が蘇ってきました。
ですが比較すると、当事者の一人称であるこの原作のほうが、
どうしてもその映像では表現しきれない心理面の印象が大きく
とても複雑な心境で読み終えました。
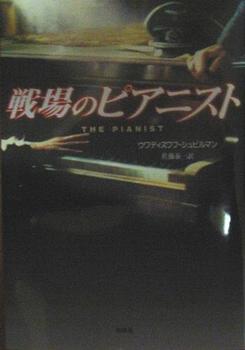
ポランスキー自身もこの本の著者と同様にゲットーで過ごした経験があるようです。
映画少年だったヴィトゲンシュタインとしては、ポランスキーといえば、
イコール「ローズマリーの赤ちゃん」のホラー映画監督というイメージですが。。
舞台となるポーランドではウクライナとリトアニア兵が中心にゲットーを荒らしまわっていたり、
ワルシャワ蜂起の場面では、コイツらはひょっとして「カミンスキー旅団」か?と
思わせるところもあって、近隣諸国との過去の様々な歴史も感じました。

一番やりきれないのが、ドイツ軍よりもゲットー内のユダヤ人警察の横暴です。
SSに媚び諂いながら、同胞のポーランド人を虐待する様は
アウシュヴィッツなどの強制収容所でもそうだった(残虐な囚人のブロック長を配置した)ように
ドイツ人、またはSSの負担を減らすべく考案された、巧妙な計画なのでしょう。
いわゆる人間の心理、「いじめ」と同じですね。いじめられている友達を助けると、
自分もいじめっ子から狙われてしまう。だからいじめる側に付く、という。。。

その絶望的な逃亡生活のなかで、著者のピアニストは薬による自殺を図りますが、
翌朝、無事に目覚めてしまい、結局「生きてて良かった」と思うシーンでは
人間の、或いはこの過酷な状況を生き延びた著者の生への執着というか
なにか考えさせられるものがあります。

この本のテーマのひとつである、著者のシュピルマンを救ったドイツ軍将校ですが、
映画を観て知っていたせいか、それほど特別な印象は受けませんでした。
実際、このような(オスカー・シンドラーとか)ドイツ人がどれほどいたのか。。
それは実行するのと、その気持ちはあっても出来なかったというのでは
どれほど違うものなのでしょうか?
力(権力や地位)のある人物と違い、そうでない人物では出来ることが限られます。
力がなくて救うことが出来なかった当時の一般のドイツ人を「何もしなかった傍観者」と
評価するのは安直だな~と改めて思いました。
まず、自分(の命、立場、名誉)、家族、親類と守るべきものがあり、
それを踏まえて赤の他人を命がけで助けようとする(考える)ことは、
現代に生きる日本人としては想像すらできません。
と、、、いろいろ考えさせられる本でした。
ウワディスワフ・シュピルマン著の「戦場のピアニスト」を読破しました。
ロマン・ポランスキー監督の映画でも有名な一冊です。
公開当時に観に行きました。だいぶ原作に忠実な映画だったんですね。
読んでいるうちに、当時観た映像が蘇ってきました。
ですが比較すると、当事者の一人称であるこの原作のほうが、
どうしてもその映像では表現しきれない心理面の印象が大きく
とても複雑な心境で読み終えました。
ポランスキー自身もこの本の著者と同様にゲットーで過ごした経験があるようです。
映画少年だったヴィトゲンシュタインとしては、ポランスキーといえば、
イコール「ローズマリーの赤ちゃん」のホラー映画監督というイメージですが。。
舞台となるポーランドではウクライナとリトアニア兵が中心にゲットーを荒らしまわっていたり、
ワルシャワ蜂起の場面では、コイツらはひょっとして「カミンスキー旅団」か?と
思わせるところもあって、近隣諸国との過去の様々な歴史も感じました。

一番やりきれないのが、ドイツ軍よりもゲットー内のユダヤ人警察の横暴です。
SSに媚び諂いながら、同胞のポーランド人を虐待する様は
アウシュヴィッツなどの強制収容所でもそうだった(残虐な囚人のブロック長を配置した)ように
ドイツ人、またはSSの負担を減らすべく考案された、巧妙な計画なのでしょう。
いわゆる人間の心理、「いじめ」と同じですね。いじめられている友達を助けると、
自分もいじめっ子から狙われてしまう。だからいじめる側に付く、という。。。

その絶望的な逃亡生活のなかで、著者のピアニストは薬による自殺を図りますが、
翌朝、無事に目覚めてしまい、結局「生きてて良かった」と思うシーンでは
人間の、或いはこの過酷な状況を生き延びた著者の生への執着というか
なにか考えさせられるものがあります。

この本のテーマのひとつである、著者のシュピルマンを救ったドイツ軍将校ですが、
映画を観て知っていたせいか、それほど特別な印象は受けませんでした。
実際、このような(オスカー・シンドラーとか)ドイツ人がどれほどいたのか。。
それは実行するのと、その気持ちはあっても出来なかったというのでは
どれほど違うものなのでしょうか?
力(権力や地位)のある人物と違い、そうでない人物では出来ることが限られます。
力がなくて救うことが出来なかった当時の一般のドイツ人を「何もしなかった傍観者」と
評価するのは安直だな~と改めて思いました。
まず、自分(の命、立場、名誉)、家族、親類と守るべきものがあり、
それを踏まえて赤の他人を命がけで助けようとする(考える)ことは、
現代に生きる日本人としては想像すらできません。
と、、、いろいろ考えさせられる本でした。




あの映画すごいですよね。命がけの商人といえば 斎藤一人さんですよ
by 天祐輔じょにー (2009-08-25 08:39)
友人に借りて、数ヶ月寝かせた後に先日一気読みしました。タイトルのセンスがちょっと引っかかっていましたが、貸してくれた友人も「このタイトルがちょっとね・・・・」と言っていました。中身はとても良いのに。
1人称で、視点が個人のものなのに、レジスタンス運動や、建物の上から眺める都市や戦闘、など急に俯瞰になったり拡大されたり、映画は見ていませんが非常に映画的な描写で、著者のセンスのよさにしびれる作品でした。
あと無人の都市の片隅に戦争終結まで5年間、後半はただただ孤独に生き延びるっていう凄さは、想像を絶する。。。 そんな中でのドイツ将校との出会い、ピアノに命を救われるって言うのがドラマチックでした。
保身のためにやりたくない音楽の仕事を請けなかったのも、戦後彼が活躍できた勝因ですね。アウシュビッツ内で音楽隊をやってた音楽家は命は無事でも他のユダヤ人たちからは恨まれて、戦後トラウマに悩まされて楽器を弾くどころじゃなくなって散々な人生送ったとかいう話を聴きましたし。。。
by IZM (2015-03-13 17:09)
6年前、最初の頃の記事を改めて読むと、恥ずかしいですねぇ。
まず、ボクが嫌いな()カッコ書きが多い!
でもこの「戦場のピアニスト」、忘れていたかったていうと、そんなことはなく、先週BSで放送していて、たまたま最後の30分だけ観たんですよ。またもや偶然・・。
正直なところ、映画の方が印象に残ってますね。それだけ映画が原作に忠実だったってことなんでしょう。
珍しく?? 一気読みされたようですから、機会があったら是非、映画もご覧になってみてください。
>アウシュビッツ内で音楽隊をやってた音楽家は命は無事でも他のユダヤ人たちからは恨まれて
なるほどねぇ。ユダヤ人っていってもフランス人だったり、ポーランド人だったり、ハンガリー人だったり国籍はバラバラだし、みんな手に職、例えば、大工、電工、細工などとアピールして生き残ろうとし、床屋だなんて言ってしまうと、ガス室送りになる前の女性の髪を丸刈りにするハメになったり・・。
ナチ党員もSS隊員もいろいろな人間がいたのと同様に、被収容者のユダヤ人にも様々な立場の人間(SSの犬のようなカポとか)が当たり前のようにいたわけですから、そのようなリアルな研究書なんか読んでみたいですね。
by ヴィトゲンシュタイン (2015-03-13 19:49)
>機会があったら是非、映画もご覧になってみてください。
是非、この本貸してくれた友人と観たいですね。 この人とはWWⅡネタでも同じ温度で話が出来る貴重な存在なのです~。
>ボクが嫌いな()カッコ書きが多い!
ヴィト様のこだわりかも知れませんが、別に気にならないし、分かりやすかったですよ。^^
いい週末をお過ごしください。
by IZM (2015-03-14 02:08)